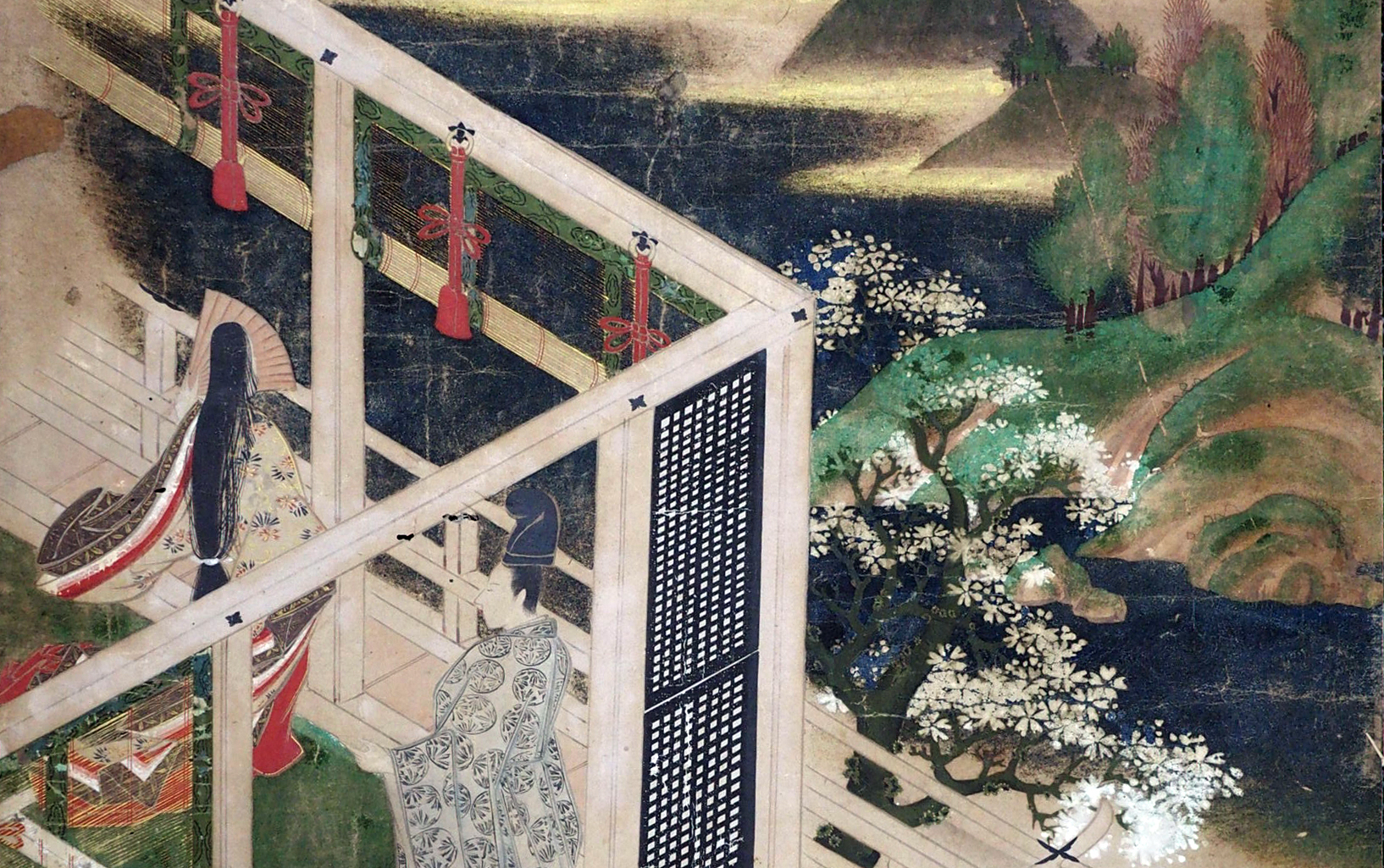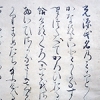重要事項の整理
- 1. けり:物語時間の現在性 01001
- 2. moodの助動詞「けり」
- 3. むとす:公式の弊害 01036
- 4. て:背景描写 01046
- 5. もの:人事の及ばぬ異物 01002
- 6. 事 01019
- 7. わざvsこと 01037:宮中サバイバルゲーム
- 8. 省筆 01034:テキストに臨む態度
- 9. 古文の構造で一番大切なこと 02057:主述関係と修飾関係の上位区分
- 10. 挿入とは 01001
- 11. 挿入の定義再び 02066
- 12. 文をまたぐ係り受け 02065
- 13. 同格ってなんだ 01001
- 14. 同格の訳「で」ってどこから 01001
- 15. 同格vs前後修飾 01052
- 16. 同格「の」の導出 01083
- 17. 前置修飾・後置修飾 01044
- 18. 分岐その一 01005
- 19. 分岐その二 01006
- 20. 分岐サイン 01011
- 21. 分岐その三 01011
- 22. 分岐その四 01012
- 23. 分岐その五 01037
- 24. 中止法って? 01052
- 25. 中止法とは 02039
- 26. 連用中止法の公式:新たな主語を立てる 01022
- 27. 連用中止法 02014
- 28. 用言並列の規則 02057
- 29. 修飾関係その一 01024
- 30. 修飾語の大原則である「交差禁止」とは 02001
- 31. 交差禁止 02063
- 32. 中間話法(描出話法) 01032
けり:物語時間の現在性 01001
「き(過去の助動詞)」や「く(来)」と現存をあらわす「あり」が共存してできた助動詞。時間や距離を飛び越えて、今ここにという感覚。早い話が、捜し物が見つかった時に今も「あった」と言う。置き忘れた瞬間から見つけだした今の瞬間まで、事実としてはその場にありつづけたことを表し、感情としてはそれを再認識することで気持ちの高ぶりを覚えたことを表す。これが「ありけり」の古文から現代文に至るまで続く姿である。形は過去形「あった」であっても、意味するところは現在この場にあるのであり、この場に突き動かされた感動なのだ。すなわち、「けり」の原義は、時間的・空間的に隔たっていたものが、今この場に呼び起こすことにある。それが過去に思いを致せば「過去回想」となり、過去から続く今の状態であれば「継続」と呼ばれ、再認識に重点を置くなら「気づき」と名を冠され、和歌の用法では呼び覚まされた感動より「詠嘆」と銘打たれるのである。「けり」は「過去の助動詞」に分類され、「き」「く」に重心が置かれて説明されて来たが、むしろ「あり」にポイントがあろう。現存こそが「けり」の本質である。日本では歌が文学の中心にあった。言葉には言霊が宿る。男女が歌を交わし合うのは、相手の歌を口にすることで、歌に込められた言霊が体内に宿るからである。精神的に感応し合うことで、気持ちを高ぶらせてゆくのであろう。その作用と最も馴染む助動詞が「けり」である。和歌に「けり」が多用されることは理由あってのことだ。文法用語として現存より広い場面に使える名前が好ましいので、呼び起こし・呼び覚まし・惹起・喚起などがよいように思う。このサイトでは熟語として馴染みやすい喚起を用いることにする。
なお、「けり」の訳し方について。物語は現在進行すると説明しながら、過去形で訳す方が自然なことも多い。それは日本語の「た」は過去だけでなく、過去から現在に至る継続も表現できるからである。訳語がどうであれ、物語を読みながら、語りを聞きながら、その場に居合わすことができるのが「けり」を代表とする言葉の現存作用である。
moodの助動詞「けり」
「かかる用もやと残したまへりける御装束一領」について。
「りける」について、「完了+過去」と考えるのが一般であろうが、そうすると、過去において「残し終えた」という桐壺更衣の行為そのもの(完了相)に意味の比重がかかることになる。この箇所の意味の比重は更衣が残したものがここにあるという現在にある。だからと言って、「けり」を過去から現在へと続く継続とはできない。更衣はすでに死んでいるのだから、「残し続ける」のはおかしい。「けり」を更衣の行為につくと考えるところに矛盾が生じるのだから、話し手である母の気分を表す法助動詞と考えれば問題は解消される。「娘が残していた(完了相:アスペクト)」を今思い出した状態にある(現在の気分=モード)という構造である。いわゆる「気づき」の「けり」に近いが、「気づき」の「けり」は、アスペクトなのかモードなのか、詠嘆の意味とどう関わるのか等、説明不足の気がする。「けり」は、過去を現在に、遠くのものを近くに、感動を言葉に「呼び起こす」働き、即ち話し手の気持ちを込めるモードの助動詞と考えるのがよいだろう。
むとす:公式の弊害 01036
「御子はかくてもいと御覧ぜまほしけれど かかるほどにさぶらひたまふ例なきことなれば まかでたまひなむとす/01036」について。
光源氏はまだ三歳だから、自らの意思で宮中を退出しようとしたわけではない。次文「何事かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへる(を)/01037」とあり、母の死もわからず、帝などが泣いている様子を不思議に御覧になっているとの描写からも、それははっきりしている。「むとす」=「…しようとする」という公式が多くの辞書に載っており、多くの注釈がこの公式を採用している。文脈上に無理があることは上で述べた通りだが、それに気付いた注釈の中には、お付きの者たちの意思をもって御子の意思としたものと、意味不明な説明を加たりする。付き人が御子の意思に従うことはあっても、逆はありえない。むろん、語り手の意識の上でも、それは同じである。ここで見逃してならないのは、「むとす」の別の使用例である。「御息所はかなき心地にわづらひて まかでなむとしたまふ(を)/01024」。「まかでたまひなむとす:A」と「まかでなむとしたまふ:B」では、尊敬語の「たまふ」の場所が違う。ここで重要なルールを復習しておく。
「同じ主体の動作が続く場合には、最後に「たまふ」を用いるのが原則」というルール。このルールを適用すると、最後に「たまふ」が付いているBは、「まかでなむ」と「す」の主体が同じ、すなわち、共に御息所の動作と考えなければならない。「む」と「す」主体が同じゆえ、「む」は一人称の意思となる。一方Aは、「まかでたまひなむ」と「す」の主体は別と考えなければならない。すなわち「す」は語り手の敬意の対象外の人である。「す」の主体は次の文中にある語だが、「さぶらふ人びと」を当てるのが一番自然だろう。「まかでたまひなむ」は、御子に向かって「さぶらふ人びと」が勧めた言葉である。「宮中から退出なさるのがよろしいかと勧め、お付きの者たちはそうしようとした」。「む」は御子に向き合う二人称の用法で勧誘を表す。「とす」は「これからしようとする」であって、まだ実際には退出する前のこと。自動詞の「す」は、自然な流れとしてそのように進行するという意味が基本であるので、自然な流れとしてそういう段取りになる、手はずとなるなど、無人称で訳してもよい。その場合でも「む」の二人称の用法は変わらない。
なお、上のルールを原則としたのは例外があるからだ。
一、なし+たまふ
二、たまふ+なし
三、たまふ+たまふ
一はふたつの動作は同じ主体。二はふたつの動作は別主体。これに例外はない。問題は三で、上のルールでは別主体と考えるべきだが、同じ主体のことも少なくない。これは個別に判断すべきだが、同じ主体で「たまふ」が繰り返される時には、ふたつの動作に時間差があるなどの理由が考えられるように思う。
て:背景描写 01046
「はかなく日ごろ過ぎて 後のわざなどにもこまかにとぶらはせたまふ/01046」について。
接続助詞「て」は完了の助動詞「つ」より発生したもので、ある動作が完了したことが従属節で記され、その結果が主節に述べられるという形式だが、主節と従属節のつながりは弱く、英語の付帯状況に近い。そのため、背景描写に多用される。
もの:人事の及ばぬ異物 01002
「人」に対立する語で、めざましさそのもの(「めざましさ」が物象化して目の前に立ち現れたという感覚)。軽視の対象として物扱いされているとする注もある。異論はないが、現代人には日常感覚では生じない「もの」への感覚、動かせない、思い通りにならない、心が通わない、違和感、圧迫感など様々な感覚を呼び覚ます点で、注意すべき重要語。この語にあったら、きわめて強い感情が働いているのだなと想像してみるとよい。
事 01019
「もの」が運命・決まり・霊的存在など人の力の及ばない存在であるのに対して、「事」は人と人との間に発生する事態。従って、解決不能というわけではないが、あまりにも敵が多く実際には解決する術を失っていた。帝の寵愛を受けて悦びはあるものの、それより遙かに苦しみが勝った。
わざvsこと 01037:宮中サバイバルゲーム
「(何事かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへるを)よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし/01037」について、解釈がまちまちなので、以下、ポイントを三点に分けて考えたい。
一、「よろしきことに」とはどんな場合のことか。
二、「かかる別れ」の「別れ」は誰との別れか。それを特定するためには「かかる」の指示する対象を明らかにするのが、論理的な読み取りである。
三、なぜこの場合の別れが「まして」なのか。以上の三点を考えるに先立ち、「かかる別れの悲しからぬはなきわざなり」について考える。
先ずわかりやすい二番から。「何事かあらむとも思したらず」とあり(「む」は未来)、今問題にしているのは母の死ではなく、父帝との別れがどういう意味を持つかの理解がないということである。それでは「かかる」は何を指すか。指示語は通常直前を受けるので、ここでも「何事からあらむとも思したらず…あやしと見たてまつりたまへる」御子の姿を指しているようにも取れる。しかしこれは個別ケースであって、これは「まして」以下で問題にされるものである。つまり、「一般的な別れにもましてこの特殊ケースは」という文の流れである。従って、「かかる別れ」はまして以下の個別ケースに入らない程度に一般化された別れを表すと読む以外にない。「まして」以下では、この場合の別れ、すなわち、父帝との別れが何を意味するのか、その重大性も理解できない幼いうちの別れと考えられる。ここでの文の焦点は別れの意味を知らないという点にある。従って、これを外して父との別れを考えれば「このような父との別れ」を理解したことになる。あとはどこまで具体性を帯びさせるかは文脈にないことなので、適宜加えることで「かかる」をより明解にさせられるだろう。
三番目「まして」を付す理由は、悲しむべき宿命なのに、それもわからないから哀れでならないのである。状況理解もできない幼さは、運命に翻弄されるばかりで、悲運に立ち向かう力がないことを含意していよう。では、その運命とは具体的に何か。御子にとって一番重要なことは、東宮になることであり、一番悲しむべき運命は東宮候補から外れることである。宮中にいれば帝に保護を得られようが、野に出ると弘徽殿の女御たちの天下となる。「悲しからぬはなきわざ」というもって回った言い方は、直截的に悲運と述べることは、語り手の身分として憚られたからである。そうした不幸を口にすることは、呪詛となってしまう。王朝人の通常感覚として、帝や東宮について表立って否定的な未来を語ることはタブーなのだ。
こういう言い方をすると、物語はすでに終わっているのに、語り手の物言いが運命を変えるのはおかしいとの反論を受けるであろう。しかし、この反論は、物語の一番重要な存在条件を無視したものである。物語が成立する場は、語り手が語るこの瞬間に物語が生み出されるのであって、すでに終わったことを述べるのではない。先が見えない、過去もおぼろげという現在にこそ物語は生きているのである。従って、語り手は口にできることとできないことが生じるのである。
一番の「よろしきことにだに」について。「よろしきこと」が何を表すのか、文脈は何も説明しないが、ある程度方向性を絞ることはできるだろう。この文のキーワードは「わざ」である。それとの対比でよく現れる言葉は「こと」であり、この文でもやはりその対比関係が用いられている。「わざ」の本義は「神わざ」であるのに対して「こと」は「人わざ」である。従って、「よろしきこと」は地上の論理、すなわち、政治的立場・地位・生まれ等の人事である。光源氏に当てはめるなら、第一皇子ではないものの、それと争える生まれが「よろしきこと」と考えていいだろう。第二皇子という特別な生まれであってさえ、父帝の元を去らねばならない運命は悲運としか言いようがないのに、ましてその意味すらわからない幼さで宮中を去るのは哀れで言葉が見つからない、ほどの意味である。もう少し分別のある年齢であれば運命に抗うこともできるが、この幼さではいかんともしがたいという気持ちが語り手にあるのだろう。
省筆 01034:テキストに臨む態度
「御使の行き交ふほどもなきに なほいぶせさを限りなくのたまはせつるを 夜半うち過ぐるほどになむ絶えはてたまひぬるとて泣き騒げば 御使もいとあへなくて帰り参りぬ/01034」について。
接続助詞「を」はとてもあいまいな接続を行う。ここでも、帝の心慮と、家の者の泣き騒ぐ様子とはつながりは見いだしにくい。その原因は、帝の心配と家の者が泣き叫ぶとの間には省筆があるからである。省筆を考えずにそのまま読むと、家の者の発言「夜半うち過ぐるほどになむ絶えはてたまひぬる」は直接話法とは考えにくい。なぜなら、帝の心配と家の者の発言とに分断があるからだ。従って、この表現は、会話内容(本来直説法)を語りを地の文(間接話法)に溶け込ませる描出話法として読むことになるが、しかし、それだと説明不足で作為的にしか読めないのだ。これはテキストが悪いのではなく、テキストに臨む態度が悪かったのである。語り手は、聞き手と共有されているものは説明を省き、物語の重要ポイントにこそ力点を置いて語るものなのだ。近代文学が求める読者への説明責任を、源氏物語の語り手に求めるのはお門違いである。語りが隅々まで十全に行われていると考えるべきではないのだ。殊に身分の低い者の動作には、状況説明がなされないことが多い。それは舞台背景であり、素通りするものなのだ。
それはさておき、この間に「帝が心配しているので、使者が御息所の家の者に問いただしたところ」という状況説明を補って読めば、「夜半うち過ぐるほどになむ絶えはてたまひぬる」全体が使者の問いに対する答えとして読むことができる。描出話法による説明を必要とせず、単なる直接話法としてよいのだ。ここに至って接続助詞の「を」がにわかに生きてくる。使者が行き来する間もなく、帝は心配でならなかったが、御息所が亡くなったと情報を得て、使者も帝の心配をよそに戻って来たのだ。
「御使もいとあへなくて帰り参りぬ/01034」について。
この「も」は難しい。「御使も」は「帰り参りぬ」に係ることは確かだが、「いとあへなくて」は御使に対する形容であろうか。すなわち、ここで語り手は使者の内面に立ち入る必要があるのだろうか。この文の話題は何であったか。それは、使者を行き来させても帝は「なほなほいぶせさを限りなくのたまはせつる」状態にあったことである。それなのにどうしたのかという結語が、接続助詞「を」を介して述べられているのである。使者そのものに焦点を当てる文ではない。「御使も」は「帝の送り出せる御使も」という状況説明であり、その実質は「帝のそうした心配も」である。しかしながら、御息所の死が確定し、「いとあへなし」となった。すなわち、取り返しのつかない状況になりおうしたのだ。「のたまはせつる+を→いとあへなし+て→帰り参りぬ」という流れである。
古文の構造で一番大切なこと 02057:主述関係と修飾関係の上位区分
「事が中に なのめなるまじき人の後見の方は もののあはれ知り過ぐし はかなきついでの情けあり をかしきに進める方なくてもよかるべしと見えたるに」について。
古文の構造で一番大切なことは、そこで切れる語(off語)なのか、後ろに続く語(on語)なのかの区別することである。源氏物語においてoff語が現れる頻度は極めて少ないので、引き続いての作業として、on語はどの語(to語)にかかるのか、(あるいはどの語(get語)がそれを受け止めるのか)を考えることになる。
古文を読む心得として、主語述語の関係を探すことからはじめることが多いが、この語がどこに続くのかを考えることを優先すべきである。それがわかった段階で、意味が特定され、必要なら主格か、連用格か、連体格かの区別がつけられる。しかしながら、この文の「進める方なし」の「進める方」と「なし」の関係はどうであろうか。「進める方はなし」と考えれば「は」は係り助詞だから修飾語となり、自然な古文ではないが「進める方がなし」と「が」を補えば、主格の格助詞だから主語と考えることになる。しかし、原文は「方なし」であって、そんな区別を必要としていないのだ。「どこに係るか、それが問題だ」
実際問題として、日常の言語活動において、主語述語なんてことを考えたりしない。言い終えたか、まだ言い終えていないか、係りと受けという意識は、頭の隅に残っているものなのだ。源氏物語の語りにおいても、これは同じであろう。主語述語なんて意識はなかろうし、頻度的にも修飾関係が圧倒的に多く現れる。主語述語にとらわれるべきではない。
挿入とは 01001
「いづれの御時にか」は、「述語がない」Aと考えるか、述語はあるが「省略されている」Bと考えるかで、読み方が変わる。Aの場合、ない述語を補うために、かかる先として述語を探すことになる。この場合は「ありけり」がかかる先となる。Bの場合、省略された述語Xを考える。「いづれの御時にか[X]」で文要素は完備されるので挿入であり、かかる先はない。
挿入の定義再び 02066
一、文頭・文中・文末を問わず、ある文の中に入っている(主節が別にあるということ)。
二、文の要素に欠落がない(欠落があれば修飾要素、欠落がないから主節から独立できる)
文をまたぐ係り受け 02065
「をり」の係る先を、どうしてこれまで理解されなかったのか。これこそが、古文と現代文の構造的な違いなのである。現代文は文を単位とし、係り受けはそれを超えないという暗黙の規則に縛られる。しかし、古文にはそもそも「。」がないから、文単位という考え方がない。特に、源氏物語は語りが基本である。例えば、女子高生の電話の内容を「。」を打って文単位に区切ったとしても、係り受けが一文内に収まるかというと、そうはならないだろう。係り受けは(現代文でいうところの)文を超えるという意識で原文にあたることが大切なのだ。このサイトで「、」「。」やカギ括弧をつけない理由は、無意識のうちに現代文の解釈方法に縛られるのを避けるためでもある。実際には、それらをうつ明確な基準がないから、恣意的な適用となるのが嫌だというに過ぎない。
同格ってなんだ 01001
英語ではAとBが同格という時、BはAの言い換えである。しかし、国文法では、Aに対して追加説明したものを同格という。同格とは、Aが主格ならBも主格というように、文中の働き(格という)が同じであることから来た呼び名なのだろう。今挙げた二点が同格を考えるポイントとなる。
一、前が主情報、後が追加情報
二、文中で同じ格として働く
「いとやむごとなき際にはあらぬがすぐれて時めきたまふ/ありけり」
同格の場合:「(A+B)/ありけり」
A:「いとやむごとなき際にはあらぬ[人]が/ありけり」
B:「すぐれて時めきたまふ[人]/ありけり」
情報の重みは A=B または A>B
主格の場合:「AがB(する)[こと]/ありけり」
A:「いとやむごとなき際にはあらぬ[人]が」
B:「すぐれて時めきたまふ[こと]」
情報の重みは述語が重く A<B
「宮中にさして高貴でない女性がいた」という情報と、「宮中で帝の寵愛を独占する女性がいた」という情報の、どちらに重きをおいて読むかで〈同格説〉〈主格説〉が決まる。決して形だけで決められるものではない。
同格の訳「で」ってどこから 01001
同格は「…で~する人がいた」と訳す。この「で」は断定の「だ」の連用形。本来は「であり」という形だが、文末の「ありけり」にかかるため「あり」が欠落して「で」が残った。
源氏物語には「連体形+ありけり」が三例あり、いずれも「こういう人があった」と想起している時の表現である。
一、「この姫君の母北の方のはらから 世におちぶれて受領の北の方になりたまへる ありけり」(蓬生)
二、「この御後見どもの中に 重々しき御乳母の兄 左中弁なる かの院の親しき人にて 年ごろつかうまつる ありけり」(若菜上)「親しき人にて」は「近臣として」の意味。
想起とは、「こういう」事態を起こした「人があった」と思い出すこと。「人/ありけり」(存在文)+「~する」(事態)と考えられる。
一、「はらから/ありけり」(存在文)+「なりたまへる」(事態)
二、「御乳母のせうと/ありけり」(存在文)+「つかうまつる」(事態)
冒頭「際にはあらぬ[女性]が/ありけり」(存在文)+「時めきたまふ」(事態)
同格では「…の人で、~する人がいた」と訳す。
主格では「…の人が~することがあった」と訳す。(「…の人がいて、~した」)
結局のところ、存在に重きをおくか(「ありけり」の意味が強い)、事態の発生(「ありけり」は形式化)に重きをおくかにかかっている。
同格vs前後修飾 01052
「けはひ容貌の面影につと添ひて思さるる(にも)」:AのB連体形(けはひ容貌:A、面影につと添ひて思さるる:B)。この「の」はいわゆる同格を表すが、意味上は倒置と考えるとわかりやすい。「面影につと添ひて思さるるけはひ容貌:B連体形→A」が元の形。この「けはひ容貌:A」に少し長い修飾「人よりはことなりし:C」を加えると、「面影につと添ひて思さるる 人よりはことなりしけはひ容貌:B連体形 C→A」となり、「思さるる」の係る先が遠くてわかりづらくなる。そこで「人よりはことなりしけはひ容貌:C→A」を前置し、「の」を補って後ろから修飾した形が「人よりはことなりしけはひ容貌 の 面影につと添ひて思さるる/C→A の B連体形」という形である。中心となる語「A」に対して、「C→A←B」のように前後から修飾すると考えるのだ。同格とは、「C→A」と「B」の後ろに「A」を補って読む読み方だが、これだと「C→A」と「B→A」の関係がどうなるのか不明のままである。単なる修飾関係とする方が余程すっきりすると思うが、国文法では、修飾語は必ず被修飾語の前にあると考えるので、後置修飾を認めていない。そこで同格という説明が考え出されたわけだが、王朝人の言語意識とこの同格説明が一致しているのか、はなはだ疑問が残る。
同格「の」の導出 01083
「長恨歌の御絵」という連体格「の」を同格「の」に見立てることで、当該箇所を導出してみよう。
同格「の」の基本形:「AのD連体形」(長恨歌の 伊勢貫之に詠ませたまへる)
「の」は同格だから「AのB、D連体形B」と同じ名詞を代入でき
変形一:「AのB D連体形B」(長恨歌の御絵 伊勢貫之に詠ませたまへる御絵)
非文法的なので、後ろの名詞は省略する
変形二:「AのB D連体形」(長恨歌の御絵 伊勢貫之に詠ませたまへる)
「亭子院/描く/せたまふ」という情報を、「D連体形」と並列の形で補えば、当該箇所ができあがる。
最終形:「長恨歌の御絵 亭子院の描かせたまひて 伊勢貫之に詠ませたまへる」
前置修飾・後置修飾 01044
「人柄のあはれに情けありし御心を 主上の女房なども恋ひしのびあへり/01044」について。
「A:人柄のあはれに」と「B:情けありし御心」は並列関係にある。正しくはAを語順転倒させた「A’:あはれなりし人柄」とBが、もしくはBを語順転倒させた「御心の情けありし」とAが並列の関係にある。この例でわかることは、前置修飾と後置修飾に隔たりがないということである。
分岐その一 01005
古典を読んでいると、話の筋が突然追えなくなることがある。しばらく読み進めば、文脈が元に復するのでなんだと落ち着くものだが、当座は冷や汗ものだ。なぜこのようなことが生じるのか、理由を考えておくと、少しは冷静に立ち回れる、かもしれない。
一、長い並列や対句がある場合
二、中止法で文意が分断され、話題が転じられる場合
三、長い修飾語がつづく場合
四、文中に挿入がある場合(文頭や文尾の挿入は文脈を追いやすい)
五、会話や心中語がはさみこまれる場合
など、これらの組み合わせも多い。
分岐その二 01006
「父の大納言は亡くなりて 母北の方なむいにしへの人のよしあるにて…」
父に関する叙述はあっさり消えるが、母に対しては延々とつづく。長い対表現による分岐の開始。読みの心構えは、「亡くなりて」とあるが、その結果どうだというのか、それを探りながら読み進めることになる。「とりたててはかばかしき後見しなければ 事ある時はなほ拠り所なく心細げなり」(娘には立派な後見がなくて心細かった)とあり、その前、母はがんばったけれどの部分が分岐となる。
分岐サイン 01011
「もてなさせたまひしほどに」が「まつはさせたまふあまりに」の言い換え「に」が繰り返されていることに注意。前の「に」がどこに続くかと考えながら読み進めると、再び「に」が出くわす。これが分岐終了の印で、帰結を迎える。
分岐その三 01011
読みの心構えとしては、帝が桐壺更衣を「わりなくまつはさせたまふあまりに(A)」どうだというのかを見てゆくことになる。
「さるべき御遊びの折々(B)」云々、「ある時には大殿籠もり過ぐして(C)」云々は(A)の具体例、その具体例をもう一度まとめ直したのが「あながちに御前去らずもてなさせたまひしほどに(D)」であり、(D)は(A)の言い換えになっている。
この言い換えこそが、分岐が戻った証拠であり、分かれた文脈をくっつける糊白の働きをするのである。
分岐その四 01012
「坊にもようせずはこの御子の居たまふべきなめり」は「と…思し疑へり」という表現から弘徽殿の心中語であることがわかる。心中語や会話の前後は一般に分岐が起こる。
分岐その五 01037
「ましてあはれに言ふかひなし」の対象は、母が亡くなった事情もわからず、父帝が泣き濡れておられるのを不思議に御覧になっている幼い光源氏の様子だから、「あやしと見たてまつりたまへるを」の「を」は格助詞。その様を「言ふかひなし」とつながる。従って、「よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」が挿入句で分岐となっている。このように挿入句は本文と独立したフレーズなので糊代なしに投げ込まれるのが特徴である。
中止法って? 01052
現代文では「終止形+読点」で文を結ぶ。実際、ものを書く場合、誰しも文という単位を意識して書く、そのように訓練させられてきた、だから文は自然な単位。しかし、これが話し言葉になると、その瞬間瞬間頭に浮かんだフレーズを繰り出しているだけで、文単位を意識して話すことはないから、会話に読点をつけるのは難しい。話し言葉の類推から古文について想像してみてほしい。古典にはまず読点がない。文という単位がそもそもあったのか不明である。終止形はあるにはあるが、挿入など文を飛び越えて係るということがよくある。源氏物語の現状に合わせるなら、読点を打つことはためらわれる。
終止形の問題を前置きにして中止法。一般には用言を修飾する連用法と、中止法の区別を立てない立ち場もあるが、ここでは、中止という言葉を重んじ、中止法とは修飾語ではないので後ろには係らず、意味もそこで休止する、しかし、文は終わらず、そこから本当に言いたいことがはじまる、そういう技法の一種と考える。前座と真打ちの関係みたいなもの、中止法がくると小休止が入って、ざぶとんが返され、いよいよ真打ちだなと思うと十中八九いけるだろう。このように連用形には連用修飾語と中止法がある。形が同じなので、連用形の修飾先を探して読み進んでもみつからない。文意もなんだか前と変わってしまっている。中止法では目先が変わるので注意を要する。これも分岐の一種である。この文「掻き鳴らし」をそれを受ける用言がない。「聞こえ出づる」にかけたのでは「言の葉も」の「も」が行き先を失う。「劣りけり」に掛けたのでは意味をなさない。「掻き鳴らし」は中止法で、状況説明である。真打ちはその後で、思い出の中の愛の言葉、今しも月の面にだぶってみえる幻の姿、そのどちらもが夢の逢瀬よりもさらにはかないものだった。
中止法とは 02039
中止法を中にはさんだ一文「A|B」と二つの文「A B」とは、情報の流れとしては「A=A、B=B」で変わりはない。しかし、中止法は「前の情報より後の情報が重要である」とのメッセージをふくむのに対して、二つの文に情報の優劣はない。この点、両者は様相を異にする。
中止法は慣性の法則と考えるとわかりやすい。それまで情報が流れていたものが、急にブレーキがかかるので前につんのめる。情報は移動しないが、重心が前方に移動する分、情報の重要度が増すのである。文学的表現では余韻という。
連用中止法の公式:新たな主語を立てる 01022
「それにつけても世の誹りのみ多かれど この御子のおよすげもておはする御容貌心ばへありがたくめづらしきまで見えたまふをえ嫉みあへたまはず ものの心知りたまふ人は かかる人も世に出でおはするものなりけりとあさましきまで目をおどろかしたまふ
「え嫉みあへたまはず」:「ず」を終止形とし、ここで文が終わると考えることも可能だが、意味上は次の文とつながるので、連用中止法と考えたい。連用中止法は新たな主語が立てられる場合によく起こる。
一、「S1+V1 S2+V2」で「S1+V1」「S2+V2」が並列関係にある時(複文の時)
「V1」は中止法になる。
二、「S1+V1 S2+V2/並列→X」
二文が並列関係にあっても、他の語(体言・用言・助詞・助動詞など)に係って行く場合は中止法としない。
なお、この文の主語は明示的でないが「世」「世の人」と考えられ、次文の主語は「ものの心知りたまふ人」である。
連用中止法 02014
「問ふなかに言ひ当つるもあり」は係る先がないので、「終止形で文が終わる」と考えるか、「連用形で文は終わるが意味的に次に続く」と考えるかの二択となる。文の終止であれば、「片端づつ見るに…言ひ当つるもあり」は文に欠落要素がないため、挿入となる。「もて離れたる」以下と位相が異なってしまう。しかし、「片端づつ見る」の結果が「もて離れたる」に影響を与えているので、意味的につながりのある連用終止と考えると自然である。なおまた、連用終止の場合、その後ろに重要表現が出てくる。この場合「言ひ当つる」ことよりも、「もて離れたる」に光源氏の関心が向いている。文のストレスからも連用中止法を支持する。
用言並列の規則 02057
「事が中に なのめなるまじき人の後見の方は もののあはれ知り過ぐし はかなきついでの情けあり をかしきに進める方なくてもよかるべしと見えたるに」について。
並列する最後以外の用言は連用形。従って「知り過ぐし」「あり」は連用形。最後の並列は次に続く形であり、「方」という体言に続くので「進める」は連体形となる。
「用言は並列される場合、最後をのぞき連用形になる」(並列の見落としに注意!)
例一、A「連用形」+B「連体形」+「体言」(Aは連用形だが、Bと並列して体言にかかる)
例二、A「連用形」+B「連体形(準体用法)」+「体言の省略」(Aは連用形だが、Bと並列して省略体言にかかる)
修飾関係その一 01024
その年の夏 御息所はかなき心地にわづらひて まかでなむとしたまふを 暇さらに許させたまはず
「その年の夏」は「わづらひて:A」「まかでなむとしたまふ:B」「許させたまはず:C」のどこに掛けるのがよいだろうか。第一に浮かぶのは、この文の情報の焦点がどこにあるかを確認し、そこに係るのではないかと予想する方法である。すなわち、御息所の病気か、宮中を出ようとしたことか、帝が許さなかったことかのいづれの意味が重要かを考えるのである。すると、息所の病気がこの文の新情報の核であり、ここが重要ポイントのように思える。しかし、文の構造としては、「わづらふ」の情報は接続助詞「て」を通して、「まかでなむとしたまふ」に入り込んでいる。御息所に関する情報はここまでで、接続助詞「を」を通して、次に主節が始まってゆく。つまり、B要素がなければ、AとCの要素はつながりを持てないのである。これを軸語という。
一般に「軸語>キーワード」というルールが成り立つ。
これは「文構造は意味に優先する」ということでもある。残るは、主節であるCに掛けるのがよいか、従属節の締めであるBni掛けるのが良いかの検討になる。「その年の夏」は従属節の冒頭にあり、主節に掛けるのは意味的関連がよほど強くないと難しい。そこで意味を考える。「その年の夏、帝は暇を出すことをお許しにならなかった」なのか、「その年の夏、病気を理由に里帰りをしようとしたが、帝は暇を出すことをお許しにならなかった」なのか。後者と考える方が自然であろう。よって、「その年の夏」は従属節の締め「まかでなむとしたまふ」に掛けるのがよいと判明する。
修飾語の大原則である「交差禁止」とは 02001
A「いとど」→「軽びたる名をや流さむ」 B「いとど」→「語り伝へけむ」
AとBどちらでも意味的にはかけられるが、「いとど」の直前「咎多かなるに」の接続助詞「に」が、「名をや流さむ」にかかることを考えると、「いとど」は同じく「名をや流さむ」にかかると考えるのが自然。さらに、Bの読みは「交差禁止」の規則に反する。
「光る源氏」→「と忍びたまひける」という係り受けがある。「いとど」は間に入っているので、外にかかることはできない。これを「交差禁止」と呼ぶことにする。「交差禁止」は和文に限らない一種の普遍文法であり、この法則がないとどこまでも係る先を探すことになり、決定できなくなってしまう。
「交差禁止」:A→Bである時、AB内にあるCが係る先はAB内に限り、Bより後ろには係ることはない。
交差禁止 02063
「いと口惜しくねぢけがましきおぼえだになくは ただひとへにものまめやかに静かなる心のおもむきならむよるべをぞ つひの頼み所には思ひおくべかりける」について。
「ただ」は前文では述語「よらじ」「言はじ」にかかるので、ここも述語にかかると考えてよさそうであるが、交差禁止の大原則に違反する。Aは意味上Cにかかる。A→C。従って、AからC内の要素は交差が禁じられているので外に出られず、Bは必然的にCにかかることになる。情報の中心もこの文では末尾の「思ひおくべかりける」にあるのではなく、「ひとへにものまめやかに静かなる心のおもむきならむよるべ」にあり、「ただ」はここにかけるのが自然なのだ。「ただ…をぞ」で係り結びの強調と呼応していることからもそれが自然だとわかる。
中間話法(描出話法) 01032
「[帝]かくながらともかくもならむを御覧じはてむと思し召すに/01032」について。
「かくながら」は地の文、「ともかくもならむ」は帝の心内語。これを地の文である格助詞「を」を介して「御覧じはてむ」につづけ、さらに「と」を介して「思し召す」につづける。「御覧じはてむ」は「思し召す」の内容だから本来は心内語である。その証拠に「む」は一人称の用法である「意思」を表す。しかし、「御覧ず」には敬語が使用されている。つまり、第三者である語り手の立場で帝の行為に敬語を用いながら、当事者である帝の立場に入り込んで心内語を語るというものである。つまり、直接話法と間接話法の境界があいまいになった話法なので、中間話法と名付けられている(描出話法とも言う)。