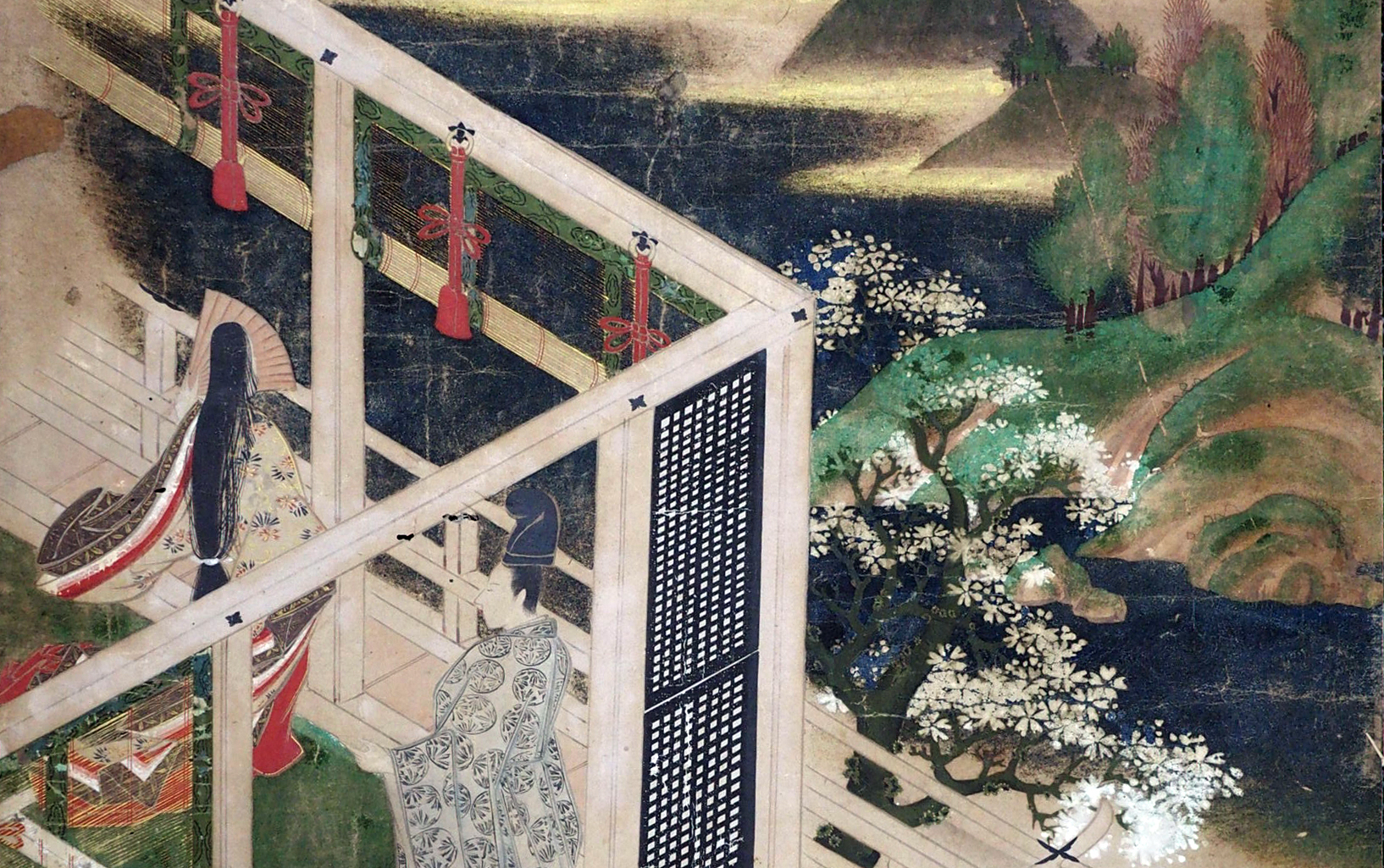何事かあらむとも思 桐壺04章02
原文 読み 意味
何事かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへるを よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし
01037/難易度:★★★
なにごと/か/あら/む/と/も/おぼし/たら/ず さぶらふ/ひとびと/の/なき/まどひ うへ/も/おほむ-なみだ/の/ひま/なく/ながれ/おはします/を あやし/と/み/たてまつり/たまへ/る/を よろしき/こと/に/だに/かかる/わかれ/の/かなしから/ぬ/は/なき/わざ/なる/を まして/あはれ/に/いふかひ-なし
何が起ころうとしているのかもお分かりでなく、側仕えの人々が泣きまどう姿や帝が涙の干る間もなく泣いておられご様子を理解もならず見守っておいでのご様子を、栄転などよい理由であっても母を亡くした父子が離れ離れになるのは悲しい重大事であるのに、まして父である帝のもとを離れ東宮資格を失いかねない里下がりとあっては哀れで言い表す言葉が見つかりませんでした。
文構造&係り受け
主語述語と大構造
- を…言ふかひなし 四次元構造
〈[御子]〉〈何事〉かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへるを /よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなる を/ 〈[我=語り手]〉ましてあはれに言ふかひなし
助詞と係り受け
何事かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへるを よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし
- 何事かあらむとも思したらず→(さぶらふ人びとの泣きまどひ・主上も御涙のひまなく流れおはします(並列)+を/格助詞→あやしと見たてまつりたまへり)+を/格助詞→(よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなり+を/接続助詞→ましてあはれに言ふかひなし)/「(…だに)…を まして…」は呼応関係。
「かかる別れの悲しからぬはなきわざなる(を)」:AのB連体形で「の」は主格/このような別れが悲しくないことはない道理である(のに)。このような別れが悲しくないはずがない(のに)。
何事かあらむとも思したらず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへるを よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし
助詞:格助 接助 係助 副助 終助 間助 助動詞
助動詞の識別:む たら ず る ぬ
- む:未来・む・終止
- たら:存続・たり・未然形
- ず:打消・ず・連用形→見たてまつりたまへり
- る:存続・り・連体
- ぬ:打消・ず・連体形/準体用法で「ぬ」の後ろに前置されている「こと」が省略されている。一般に同格とされるが、同格ではない。「よろしきこと」は母集団、その中にさえ「悲しからぬこと」(部分集合)がないという道理はないとの意味。従って同格たりえない。それにしてもどうして「悲しからぬはなきわざなり」と二重否定を用いて、もってまわった言い回ししたのか。後ほど、これについて考察したい。
敬語の区別:思す さぶらふ 御 おはします たてまつる たまふ
何事かあらむと も思したら ず さぶらふ人びとの泣きまどひ 主上も御涙のひまなく流れおはしますを あやしと見たてまつりたまへる を よろしきことに だにかかる別れの悲しからぬ はなきわざなる を ましてあはれに言ふかひなし
尊敬語 謙譲語 丁寧語
古語探訪
何事かあらむとも思したらず 01037
父の目が利く宮中を出て母の実家で暮らすことになるが、後ろ盾のない光の君に待ち受けている将来不安を何も感じないこと。「む」はこれからの出来事。これを無視して、母の死について何も理解しないは大間違い。
よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし 01037:父帝のもとを離れることの意味
よろしき生まれにあっても、母の死によるこうした父子の別れは悲しからざる宿命であるのに、まして待ち受ける運命について何も知らない御子の様子は言葉が見つかりませんでした。ざっと、こんな訳だが、「悲しからざるはなきわざなり」について簡単に補足しておく。どうもここの理解を欠くために、一文の読み取りがつじつま合わせに終わっているきらいがあるからだ。
この文の肝は「わざ」という特殊語である。「わざ」とは本来、神意、すなわち人業をはるかに超えた意思の働きである。そこから宿命・運命・摂理などの意味や、もう少し人よりだと道理などの意味となる。一文の論理を現代文化すると、「よろしきこと」の中にあっても、「かかる別れ」は悲しからざることはない「わざ」であると言うのだ。さらに二重否定を単純化すると「悲しいはずの道理」とか、「悲しい宿命」などの意味が浮かび上がる。ここでピンと来なければならないのは、この文の前半で、御子は今の状況を理解していないという点である。御子は理解していないが、こうした別れは悲しからざる運命なのだと、語り手は説いているのである。それなのに(接続助詞の「を」)、将来について何も理解していない御子の様子はまして哀れでならないという論旨である。ではその運命とな何か。なにゆえ悲しまざるを得ないのか。それを理解しないと、お涙ちょうだいで終わってしまう。「サバイバルゲーム」を参照ください。
主上 01037
帝。
あやし 01037
合理的な解釈ができないことから生じる感情。
〈テキスト〉〈語り〉〈文脈〉の背景
サバイバルゲーム 01037
「よろしきことにだにかかる別れの悲しからぬはなきわざなるを ましてあはれに言ふかひなし」について、解釈がまちまちなので、以下、ポイントを三点に分けて考えたい。
一、「よろしきことに」とはどんな場合のことか。
二、「かかる別れ」の「別れ」は誰との別れか。それを特定するためには「かかる」の指示する対象を明らかにするのが、論理的な読み取りである。
三、なぜこの場合の別れが「まして」なのか。以上の三点を考えるに先立ち、「かかる別れの悲しからぬはなきわざなり」について考える。
先ずわかりやすい二番から。「何事かあらむとも思したらず」とあり(「む」は未来)、今問題にしているのは母の死ではなく、父帝との別れがどういう意味を持つかの理解がないということである。それでは「かかる」は何を指すか。指示語は通常直前を受けるので、ここでも「何事からあらむとも思したらず…あやしと見たてまつりたまへる」御子の姿を指しているようにも取れる。しかしこれは個別ケースであって、これは「まして」以下で問題にされるものである。つまり、「一般的な別れにもましてこの特殊ケースは」という文の流れである。従って、「かかる別れ」はまして以下の個別ケースに入らない程度に一般化された別れを表すと読む以外にない。「まして」以下では、この場合の別れ、すなわち、父帝との別れが何を意味するのか、その重大性も理解できない幼いうちの別れと考えられる。ここでの文の焦点は別れの意味を知らないという点にある。従って、これを外して父との別れを考えれば「このような父との別れ」を理解したことになる。あとはどこまで具体性を帯びさせるかは文脈にないことなので、適宜加えることで「かかる」をより明解にさせられるだろう。
三番目「まして」を付す理由は、悲しむべき宿命なのに、それもわからないから哀れでならないのである。状況理解もできない幼さは、運命に翻弄されるばかりで、悲運に立ち向かう力がないことを含意していよう。では、その運命とは具体的に何か。御子にとって一番重要なことは、東宮になることであり、一番悲しむべき運命は東宮候補から外れることである。宮中にいれば帝に保護を得られようが、野に出ると弘徽殿の女御たちの天下となる。「悲しからぬはなきわざ」というもって回った言い方は、直截的に悲運と述べることは、語り手の身分として憚られたからである。そうした不幸を口にすることは、呪詛となってしまう。王朝人の通常感覚として、帝や東宮について表立って否定的な未来を語ることはタブーなのだ。
こういう言い方をすると、物語はすでに終わっているのに、語り手の物言いが運命を変えるのはおかしいとの反論を受けるであろう。しかし、この反論は、物語の一番重要な存在条件を無視したものである。物語が成立する場は、語り手が語るこの瞬間に物語が生み出されるのであって、すでに終わったことを述べるのではない。先が見えない、過去もおぼろげという現在にこそ物語は生きているのである。従って、語り手は口にできることとできないことが生じるのである。
一番の「よろしきことにだに」について。「よろしきこと」が何を表すのか、文脈は何も説明しないが、ある程度方向性を絞ることはできるだろう。この文のキーワードは「わざ」である。それとの対比でよく現れる言葉は「こと」であり、この文でもやはりその対比関係が用いられている。「わざ」の本義は「神わざ」であるのに対して「こと」は「人わざ」である。従って、「よろしきこと」は地上の論理、すなわち、政治的立場・地位・生まれ等の人事である。光源氏に当てはめるなら、第一皇子ではないものの、それと争える生まれが「よろしきこと」と考えていいだろう。第二皇子という特別な生まれであってさえ、父帝の元を去らねばならない運命は悲運としか言いようがないのに、ましてその意味すらわからない幼さで宮中を去るのは哀れで言葉が見つからない、ほどの意味である。もう少し分別のある年齢であれば運命に抗うこともできるが、この幼さではいかんともしがたいという気持ちが語り手にあるのだろう。