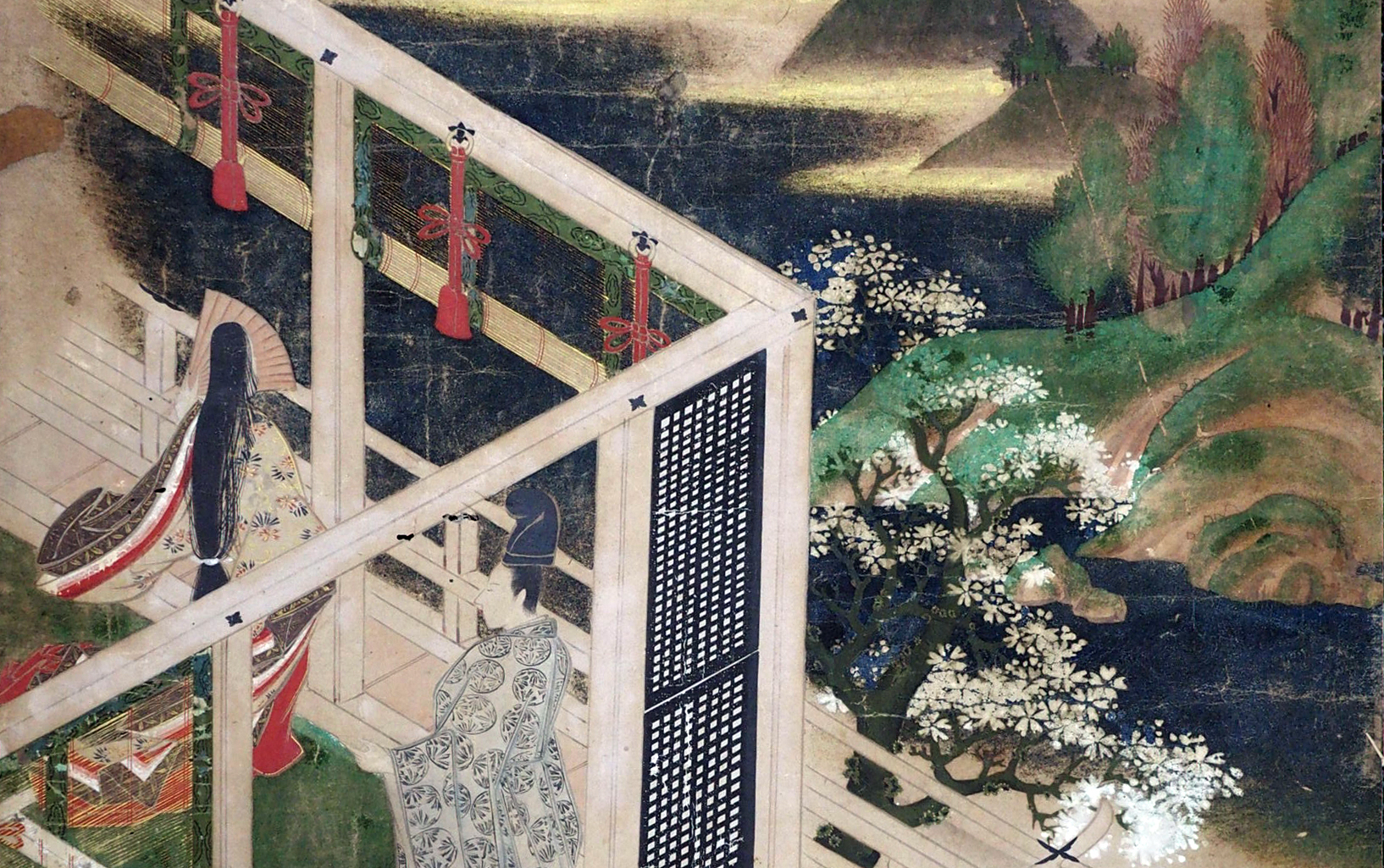伊勢物語 初段 初冠
参考「忍ぶの乱れ」『伊勢物語』初段
※原文:学習院大学所蔵の影印本(小林茂美校注『伊勢物語』新典社)
・ひらがなのルビ:ひらがなの原文に漢字を補う
・カタカナのルビ:漢字の原文に読み方を補う
初冠:
二説あり、A初めて冠を付ける儀式である元服を指すとの解釈と、B初めて爵位を得る叙爵を表すとの解釈がある。冠(かうぶり)は「得」「賜(た)ぶ」「給(たま)ふ」などの動詞を取る場合は、叙爵の意味となり、「す」というサ変動詞では、叙爵の意味を表せないという。叙爵は受けるものだから、サ変動詞と続けられないのである。従ってB説は一般に否定されている。しかし、小松茂美氏の説、「貴族の子弟が元服して、初めて従五位をいただくこと。「元服」と解しては不十分。成年式のための物忌みに服する期間、そのしるしとしてつけるのが冠。これを脱いで初めて元服したことになる」は、なお検討に値する。つまり、初冠は、初めて冠をつけることであり、その行為はサ変動詞と接続可能である。通説は、初めて冠をつけることを、元服とみなすが、これは元服にいたる物忌みの期間であって、元服式の途中であり、元服は終わっていないとのことである。両説がともに可能であれば、判断を下す基準は、この語そのものにあるのではなく、どちらの説がよりこの段全体をより深く理解させてくれるかという基準になる。諸説とも単に注するのみで、そう読むことで全体がどのように生き生きと読めるかという検討がない点、必要十分条件を満たしていないと思う。結論から先に言えば、この語の理解にとって重要なことは、元服でも従五位の位を得たことでもなく、まさに成人途中の物忌み期間に、「女はらから」との恋愛事件が行われた点にあるのだ。「初冠し」とは、外延としての意味は、初めて冠を身につける行為そのものを指し、その内包するところは、成人途上の物忌み期間であることを示し、その行為の結果として、冠を付けた状態で狩に来ているのである。物忌み期間であることがなぜに大事かは、以下の注釈で明らかになるであろう。
しる由:
二説あり、A「統(し)る」と漢字を当て、領地を所有しているのでと考える説と、B「知る」と漢字を当て、知人の縁でと考える説とに分かれる。しかし、相続するなどして自分が領地を所有しているなら、「由」に接続するのはおかしい。由は間接的理由であり、直接的理由は故(ゆゑ)である。いまだに「統る由」とする注釈があるのはどうかと思う。
奈良の京春日の里:
春日の里は今の奈良公園あたりであり、奈良市内となるが、平城京は、今の市内より西にあったので、春日の里は東のはずれである。さらに時代背景として、京都に遷都が行われた後であるから、廃都の外れ、人の住まない場所である。本文の読解とは直接関係ないが、伊勢物語の主人公とされている在原業平の祖父は、平城(へいぜい)上皇である。平城上皇は、平安遷都後も平城京に残り、再度都を戻そうとした人物。薬子(くすこ)の変で敗れ、業平の父は、親王から人臣に下ることで在原姓を得て生き延びる。業平は、世が世であれば、帝にも成り得た物語の主人公としての資格を十分に備えているのである。このように平城京と業平とは密接なつながりがあるのである。
狩:
鷹狩り。
去ぬ:
行くが移動途中に重点があるのに対して、去ぬは行き着いた先に重点があると説明されている。
なまめいたる:
なまは、まだ熟さない状態。めくは、そのように見える。つまり、すでに成熟していながら外見には初々しく見えるさま。男が、成人と子供の中間にあるのと、対をなし、女も成熟しながらも初々しいのである。
女はらから:
諸説ともに女姉妹、すなわち姉と妹と考え、第四十一段の「昔、女はらから二人ありけり」と結びつける。「女はらから」には姉妹(sisters)の意味もあるが、ある人の同腹の姉または妹(one’s sister)の意味もある。こちらの意味を検討せずに、頭ごなしに注をつけるのは危険である。まず、初段のみで女が二人いなければ文が通じない箇所は一カ所もない。逆に、女が二人であることは自然さに欠ける。次に第四十一段と結びつけるのは、「女はらから」の文字だけであり、内容的に初段と関わりを見ることはできない。この歌はこの歌の心持ちであるという、歌を歌で解釈する書き方は似ているが、「女はらから」の文字がなければ、初段と第四十一段はつながりを見る方が無理である。そもそも「女はらから二人」という表現と、「女はらから」という表現は同じなのだろうか。「主のはらからなる主」百一段は、行平の同腹である業平の意味であり、「女はらから」とあるだけでは、姉妹二人とも、誰かの姉(妹)とも区別はできないのである。
テキストの絡まり
垣間見る:
男が見知らぬ女性と知り合う恋愛の常套手段。
思ほえず:
想像もしなかったことだがの意味を表し、かかる場所が二説に分かれ、A「(女はらからが)いとはしたなくてありければ」にかける説と、B「心地まどひにけり」にかける説がある。自分の気持ちが動揺したことが予期しなかったというBの解釈はおかしい。心の動揺の直接原因である女はらからに焦点が合ってなければならない。「いとはしたなくてありければ」にかけるのが正しい。しかし、その意味は正しく理解されていない。
ふる里:
廃都のこと。
はしたなくてありければ:
「はしたなし」は規格に合わない意味の「はした」に強調の「なし」がついたもの。不作法・情に欠けるなど悪い意味で使われる語である。しかるに諸注は、廃都に不釣り合いな美人がいると解釈し、その間の意味の差を埋めようといろいろ言葉を用いるが、なんとも独り合点で説得力にかける。ここの正しい意味は、やはり男にとって悪い意味なのだ。つまり、男がどう手を出そうが、その女を獲得できない状態で女はいたということ、女は神官として、男を寄せ付けない女なのである。若い美人であれば当然若い美男子と恋に落ちるはずであるが、それを許されない状態として女はそこに住んでいたという意味が、「はしたなくてあり」である。「て」は、そのような状態での意味。先の「思ほえず」は、こんなところに美人がいることが意外だったのではなく、美人であるのに男を寄せ付けないという状況が「思ほえず」なのである。
心地まどひにけり:
「まどひ」は解決策がなくて窮すること。諸注は、思わぬ美人に気が動顛してと読むが、これも間違いである。相手が結界の中にいて、手を出すに出せず、どうにもなりそうになくて窮しているのである。
男の:
「の」は主格で、「書きてやる」が述語。
狩衣:
鷹狩りの服装。狩はもと吉凶を占う行為であり、狩衣はそのための小忌衣(おみごろも)であった。のちに晴れの衣装となり、平安時代には貴族の平常の服となった。
信夫摺:
二説あり、A陸奥(むつ)の国、信夫郡の産とする説と、B忍草(しのぶぐさ)を衣の下に敷き、上から染料を擦りつけて忍ぶ草の形を染め出したものとの説がある。型染めであれば、忍草である必要がないとの理由で、B説は少数派であるが、それは間違いである。忍草の葉の形は、小忌衣であり、物忌みの服装である。元服の途中であって、物忌みの期間であることの証しがここにあるのだ。信夫郡の産出では後の歌の「乱れ」が意味をなさない。染料を擦りつけて染めるので、液につけて染める草木染めのようなやり方よりもムラができる。それが乱れなのだ。
春日の野:
春日の里
若むらさき:
紫は高貴な色であり、高貴な出である女はらからを象徴するとともに、男の狩衣の色を表す。
すり衣:
紫色で摺り込んだの意味と解釈されているが、女の存在を男の心に擦り込んだの意味をもかける。この点がこの歌の要だ。
しのぶの乱れ:
忍ぶ気持ちが抑えつけられないの意味と、信夫摺りにムラがあることと諸注は解釈するが、女が神官でないなら、忍ぶ必要はない。ここは気持ちを抑えなければならない必然性があるから忍んでいるのである。それは相手が神官であるだけでなく、自分が物忌みの期間であることも加わっている。これを破ってしまいそうだというのだ。このどうにもならない苦しみに思いを馳せなければ、この歌を理解したことにならない。単に、いい女をどう料理しようかといった軽い歌とはまったく違うのだ。
をいつきて:
三説ある。A「老(お)ひづきて」を当て大人ぶっての意味、B「追ひつきて」を当て即座にの意味、C「追ひ継ぎて」でちらし書きをせずの意味。Cは源氏物語の「陸奥紙に追ひつぎ書き給ひて」と出て来るのが根拠となっている。Aでは仮名の「を」を「お」に読まなければならない無理があるし、あとに作者(あるいはこの段の編者)の注が入るのに、ここで草子地が入るのも不自然である。Bは現在主流な解釈だが、男の窮地からして、すぐに歌が出たと読むことには無理がある。恋文であればいかに美しく書いて相手に訴えるかが問題になるが、そうした余裕がないことが、この場の解釈としてはふさわしい。
・「ヒ」:原文になく補った。
ついでおもしろき:
機会。ちょうど若紫の信夫摺の狩衣を着ていたことが、成就しない恋の相手に苦しみを訴えることにふさわしかったこと。この状況を喜んだわけではない。
みちのくの:
信夫にかかる枕詞。
忍:
忍草と地名の信夫をかける。「みちのくの忍もぢずり」が「乱れ」を呼び起こす序詞。
たれゆゑに:
あなた以外の誰のために
我ならなくに:
そんな私ではないのに。
心ばへ:
趣向。男の歌の主旨が左大臣融の歌の主旨と合致していたことをいう。
昔人:
男をさらに時間をおいて一般化することで、逆に業平であることを匂わせる。
いちはやきみやび:
いちはやきのいちは、神威霊威をあらわし、それらがさっと恐ろしい力で働くことがいちはやしの原義であり、手向かいできないほど激しい力が働くことであって、早さを意味する言葉ではない。諸注はすばやさ、機転の効き方ととるが、原義にそぐわない。これは性衝動の激しさを言うのであろう。それをその場の状況に合わせた歌というソフィスティケートされた形で表現することが「みやび」なのである。性の激しさとこれを包む文化的洗練がいちはやきみやびである。つまり、自分が物忌み中であり、相手は神官であり、いずれにしても恋の成就はかなわないという状況の中で、どうにもならない性衝動を、その場にふさわしい歌に昇華したことが、いちはやきみやびなのである。歌を書き付けたのが、紙でなく信夫摺りという小忌衣を切り取って送ったという、とっさの行為に、タブーを破ったことが、あるいは今後もそうしたタブーを破るであろうことが、象徴的にあらわれているところに、この段の文学的魅力がある。
河原大臣の歌なり(左大臣融、寛平七年八月二十五日薨ず七十三)
在中将より幾(いく)ばくの先達にもあらざるを如何(いかん)業平よりも三歳しか違わない融の歌を本歌にしているのはおかしいのではないかという、定家のメモ。
源氏物語の元型
女はらから再考
この段に関連する詞書きとして「在中将集」と「業平集」が知られている。それぞれ原文を引く。
かすかのゝのわかむらさきのすり衣 しのふのみたれかきりしられす(在中将集)
かすかのゝわかむらさきのすりことも しのふのみたれかきりしられす
返し
みちのくのしのふもちすりたれゆへに みたれそめにしわれならなくに(業平集)
どちらの家集も相手の女性はひとりと読むの自然である。この二家集をもって伊勢物語の本文が女二人でないことの証左にはならないが、初段の設定が女二人である必要はなく、女はらからには、姉妹のほかに、誰かの姉または妹の意味があり、後者の意味であれば女はひとりとなる。どちらが自然かというだけのことである。
なお、「みちのくの」の和歌を女の返しとすれば、伊勢本文とは意味が異なってきて、「われならなくに」は、思わず知らずの意味から、わたし以外の誰かのせいであなたは心を乱しているのでしょうとの意味になる。