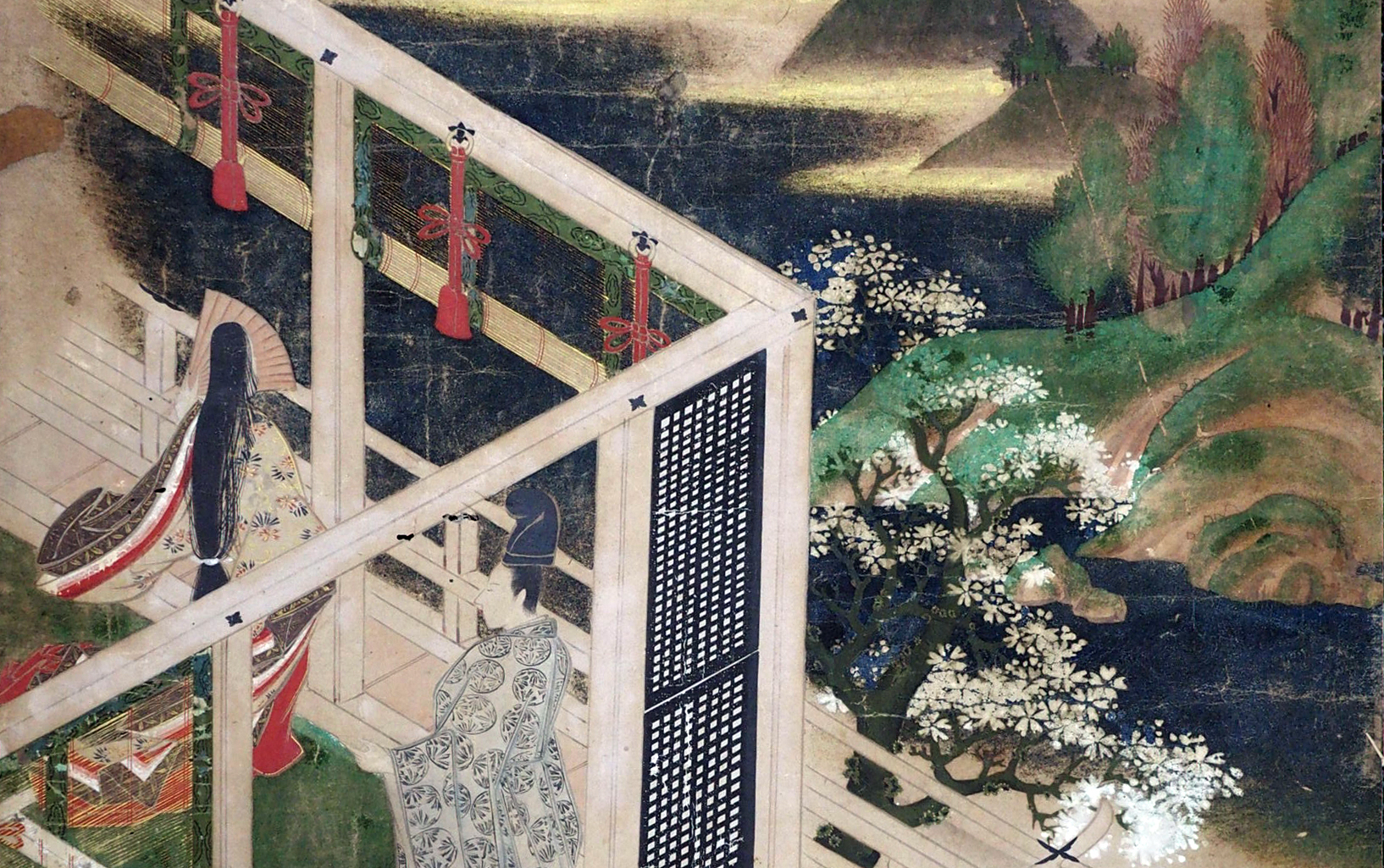元の品時世のおぼえ 帚木03章07
原文 読み 意味
元の品 時世のおぼえうち合ひ やむごとなきあたりの内々のもてなしけはひ後れたらむは さらにも言はず 何をしてかく生ひ出でけむと 言ふかひなくおぼゆべし
02038/難易度:☆☆☆
もと/の/しな ときよ/の/おぼエ/うちあひ やむごとなき/あたり/の/うちうち/の/もてなし/けはひ/おくれ/たら/む/は さらに/も/いは/ず なに/を/し/て/かく/おひいで/けむ/と いふかひ-なく/おぼゆ/べし
(頭中将)祖先の血筋がよく今の世の評判もそれに見合うものであり、位人臣を極めた家柄でありながら、内輪での立ち居や気品がひけを取るようでは、お話にもならず、何をどうしてこんな育ちをしたろうかと言う甲斐なく思えましょう。
文構造&係り受け
主語述語と大構造
- と…おぼゆべし 四次元構造
〈元の品時世のおぼえ〉うち合ひ やむごとなき〈あたり〉の 内々の〈もてなしけはひ〉後れたらむ〈[娘]〉は /さらにも言はず/ 何をしてかく生ひ出でけむと 〈[発言者]〉言ふかひなくおぼゆべし
助詞と係り受け
元の品 時世のおぼえうち合ひ やむごとなきあたりの内々のもてなしけはひ後れたらむは さらにも言はず 何をしてかく生ひ出でけむと 言ふかひなくおぼゆべし
「元の品時世のおぼえうち合ひ」「やむごとなき」(並列)→「あたり(の)」
「あたりの内々のもてなしけはひ後れたらむ」:AのB連体形、「の」は同格(「後れたらむ」の主語は「もてなしけはひ」であり、主格の席は埋まっている。従って同格となる)
「後れたらむは」→「言ふかひなくおぼゆべし」
「さらにも言はず」:挿入
古語探訪
うち合ひ 02038:その身にふさわしい
源氏物語での用法は「装束どものうちあはず/*」〈真木柱〉、「親などもものし給はぬ人なれば……打ち合はぬ様に見え奉る事も/*」〈夕顔〉など、「あるものが(その身に)添う・ぴったりくる・ふさわしい」という意味で使用される。家柄と評判が揃うではなく、家柄に見合うだけの評判がある。
元の 02038
いにしえからの、もともとのの意味である。先の頭中将の議論は「成り上がり者と没落貴族」がテーマであり、こちらは「昔から変わらず身分の高い女性」がテーマである。
時世の 02038
「現在の」で「元の」と対比する。
やむごとなき 02038
地位・身分がこの上なく高い。大臣クラスを指す。
あたり 02038
ここでテーマとなっている女性の所属する集団。具体的には「家」と考えてよい。「やむごとなし」は身分がこの上なく高いの意味である。ここまで訳すと、「いにしえからの格式も現在の世評もともにふさわしく(高い)、地位も最上級の家柄」となる。
内々 02038
格式や世評が家を外から評価するのに対して、その女性とつきあい、その家に出入りするようになって、実際に内輪で目の当たりにした時のその女性自身に対する評価である。外的条件である家柄がいくら最上の階級であっても、内的条件である「もてなし・けはひ」が劣るようではお話にならない。
もてなし 02038
多義語であるが、「けはひ」と対をなしている点で、態度ととる。
けはひ 02038
同じく多義語であるが、「もてなし」と対をなしている点で、品位ととる。
〈テキスト〉〈語り〉〈文脈〉の背景
頭中将と左馬頭のキャラクターの違い 02038
この文と次の文の発言者は不明であるが、左馬頭は上の上の品である光源氏の面前で、仮定であっても上の上の品に対して「言ふかひなくおぼゆべし」と痛烈に批判できる立ち場にはないと思われる。頭中将にしてもそれは同じであるが、一つには光源氏に対する馴れ馴れしさから、今一つは直前で「中将憎む」とあり、やや腹を立ててこの議論に遠慮はいるまいと腹を決めたものと思われるからである。遠慮を捨てることで議論は白熱するのである。これも作者による舞台設定の心配りであろう。
発言者再び 02038
「元の品」以下の発言について。『新体系』は頭中将か左馬頭か不明とするものの、他の諸注は左馬頭の論とする。しかし、以下の理由により、頭中将の発言と考える。
一、議論がいまだ抽象論を出ない。
二、これに続く「おほかたの世につけてみるには咎なきも」で始まる左馬頭の論の冒頭部分は、一般論であり話の枕的な意味合いが強く、また、頭中将の論のもともとの話題である「そも、まことにその方をとり出でむ選びに」とパラフレーズするものであるゆえ、ここで話者が変わったと考える方が自然である。
三、最上の位の女性について触れるとき、左馬頭は「君達の上なき御選びには、まして、いかばかりの人かはたぐひたまはむ」と直接明言することを避けているが、この発言内では、最上級の女性でも仕草や気品が難がある場合、「さらにも言はず、何をしてかく生ひ出でむけむと言ふかひなくおぼゆべし」と辛らつに批判している。身分の高くない左馬頭の論とは考えにくい。
四、光るは「おほかたの」以後の左馬頭以後の論に対して無反応な聞き手に回るが、ここでは「上の品と思ふだにかたげなる世を」と、話者は光るの心内が批判的であることを語っている。この批判は議論の中身に対するより、頭中将に対するライバル意識が反映されている。左馬頭へはライベル意識がないので、話に関心を示さない。