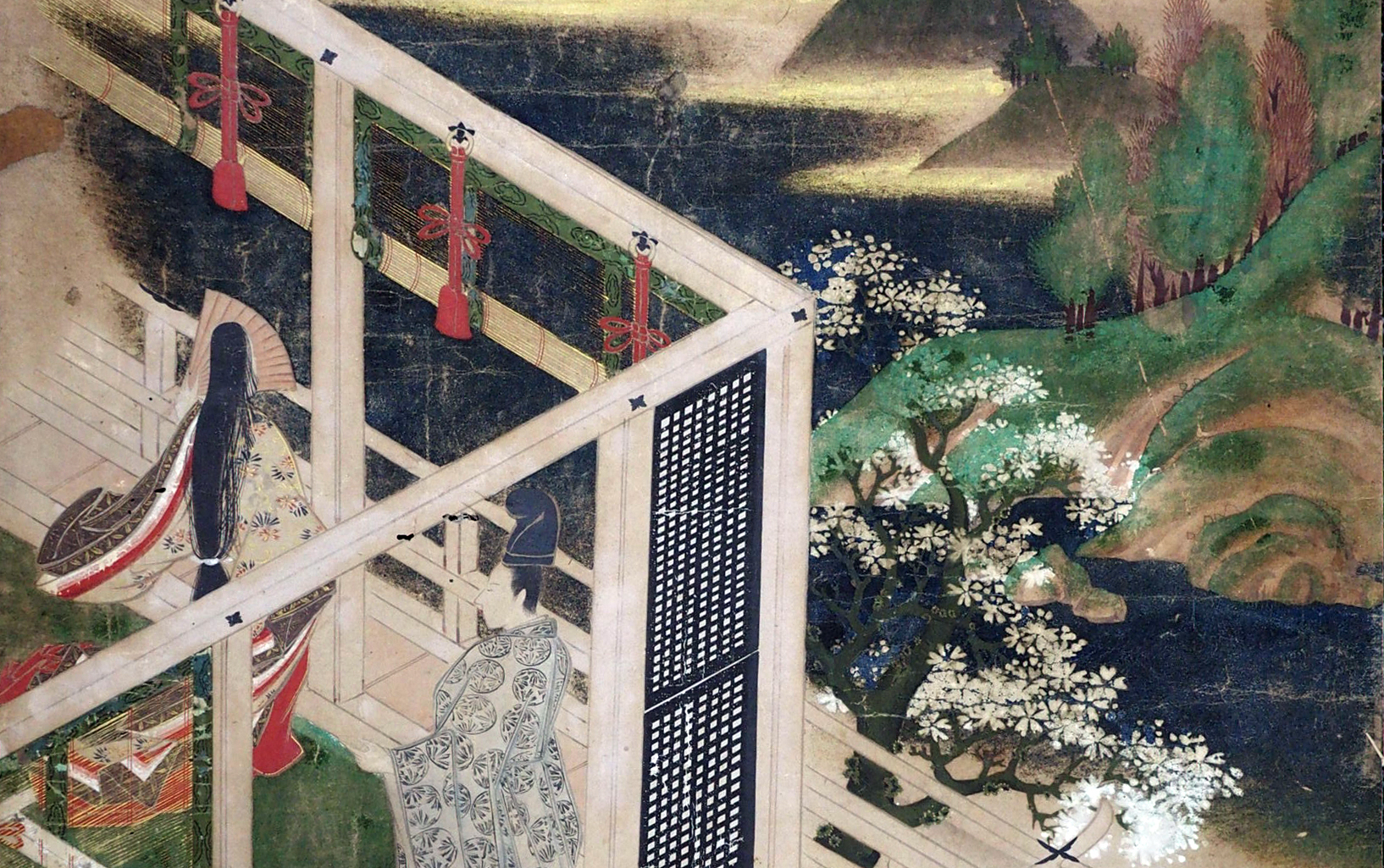見る人後れたる方を 帚木02章14
原文 読み 意味
見る人 後れたる方をば言ひ隠し さてありぬべき方をばつくろひて まねび出だすに それしかあらじと そらにいかがは推し量り思ひくたさむ まことかと見もてゆくに 見劣りせぬやうはなくなむあるべきと うめきたる気色も恥づかしげなれば
02022/難易度:☆☆☆
みる/ひと おくれ/たる/かた/を/ば/いひかくし さて/あり/ぬ/べき/かた/を/ば/つくろひ/て まねび/いだす/に それ/しか/あら/じ/と そら/に/いかがは/おしはかり/おもひくたさ/む まこと/か/と/み/もて/ゆく/に みおとり/せ/ぬ/やう/は/なく/なむ/ある/べき/と うめき/たる/けしき/も/はづかしげ/なれ/ば
(頭中将)後見人は見劣りする方面を隠して言わず、ありのままでよい面も聞こえよく伝えるものだから、そんな立派なはずはあるまいと見もせぬうちにどうして当て推量で正体を見抜きけましょうか。本当だろうかと一緒に暮らしてゆくうちに、がっかりせずにすむなんてことはあるべくもないのにと、大袈裟に嘆息する表情もいかにも誇らしげなので、
文構造&係り受け
主語述語と大構造
- も恥づかしげなれば 六次元構造
〈見る人〉後れたる方をば言ひ隠し さてありぬべき方をばつくろひてまねび出だすに / @〈それ〉しかあらじと@そらにいかがは推し量り思ひくたさむ / まことかと見もてゆくに 見劣りせぬやうはなくなむあるべきと 〈[頭中将]〉うめきたる〈気色〉も恥づかしげなれば
助詞と係り受け
見る人 後れたる方をば言ひ隠し さてありぬべき方をばつくろひて まねび出だすに それしかあらじと そらにいかがは推し量り思ひくたさむ まことかと見もてゆくに 見劣りせぬやうはなくなむあるべきと うめきたる気色も恥づかしげなれば
「後れたる方をば言ひ隠し」「さてありぬべき方をばつくろひて」(並列)→「まねび出だす」
「それしかあらじとそらにいかがは推し量り思ひくたさむ」:挿入句
「恥づかしげなれば」→「うちほほ笑み(て)/02023」→「のたまへ(ば)/02023」
古語探訪
うめきたる気色も恥づかしげなれば 02022:悪乗りする光源氏
女性体験ではさして変わらぬ光源氏と頭中将であるが、その性格からさも自分は経験豊かであるかのように得意気に語る頭中将を光源氏は面白がっているのであって、その語る話に特別な関心があるわけではない[補02002]参照。
見る人 02022
親の場合もあれば、後見の場合もある。男との間に入って、女を世話する者。
さてありぬべき方をば 02022
「そのままであってよい方面を」すなわち、「そのまま伝えればよいのにそれを」との意味である。
まねび 02022
そのまま伝える。本人が伝えたい通りに伝えるの意味だが、その前に「つくろひて」とあるから、すでに作為した後で、事実通りですと伝えることを言うのであろう。
しかあらじ 02022
見る人が「まねび出」した話を、うそだと見破ること。
そらに 02022
会わずに。目算で。
思ひくたす 02022
そしる。
見もてゆく 02022
時間をそれなりにかけて世話をする。
なくなむあるべき 02022
なくてすむはずがない。必ず見劣りする。
〈テキスト〉〈語り〉〈文脈〉の背景
性格喜劇 02022
諸注ともに「はづかしげ」を頭中将が経験豊富で、うぶな光源氏はこれに圧倒されていると説明する。だが、年齢的に考えても。光源氏と頭中将の女性経験はそんなに差があったのだろうか。この段の最初で、光はすでに世間では色好みとして通っているし、二の町からの手紙だけでも数多く受け取り、「よくさまざまなる物どもこそはべりけれ」と頭中将自身が感嘆している。初体験をすでに元服した夜にすませ、通説に従えばそれから五年が経っている。いくらまめだちたる性格と、この段のはじめでは規定されていても、以後の光の行動から察するに、その五年間、ほとんど女性経験がなかったなどと読む方が無理である。
ここで、頭中将が光に馴れ馴れしい態度を取ることが、幾度も幾度も繰り返されていることを思い出すべきだ。頭中将のこの性格が、雨夜の品定めの議論に反映していると読まなければ、導入部は意味をなさなくなる。経験の差による性教育の教え手と聞き手という役割分担ではなく、さしたる経験の差もないのに得々としゃべる浮薄な頭中将と寡黙で自省的な光源氏との対立劇(性格喜劇)である。
後回しになったが、語彙レベルにおいても、こうした読みは要請されている。諸注では無視されているが、「恥づかしげ」の「げ」に注意すべきである。本当は立派でもなんでもないが、こちらが気がひけるほど立派そうな様子をしているとの意味をふくんでいる。ややあとの表現だが、おなじく頭中将に対して「くまなしげ」と表現し、左馬頭に対して「くまなし」と使い分けているのも同じ意識である。これは後述する。
追、「女の、これはしもと難つくまじきはかたくもかるかなと、やうやうなむ見たまへ知る」という言い回しは、おそらく大人ぶった若造の常套句を出ないのではないか。オレも最近酒の味がやっとわかるようになったゼ、というのと変わりない。あるいはそうした態度を見せることが、当時の貴公子のはやりであったのかも知れない。現実の恋愛は平仲物語的な滑稽譚に終ることが多かったろうから、それを男性側からの照れ隠しとしてこういう議論がさかんだったろう。今でも男が集まればこの手の話題は絶えない。ただ、光源氏の頭の中にある女性は藤壺の宮であり、頭中将が女を見る目で光源氏は女性を見ていない。その差が、品定めへの関心の差につながってくるだろう。繰り返すが、光は頭中将の議論を有難く押しいただいているどころか、まともに聞いていない。光源氏の心に響いていないながら、後の光源氏の人生を規定するように物語が進行してゆくところが、運命劇として面白いのだ。