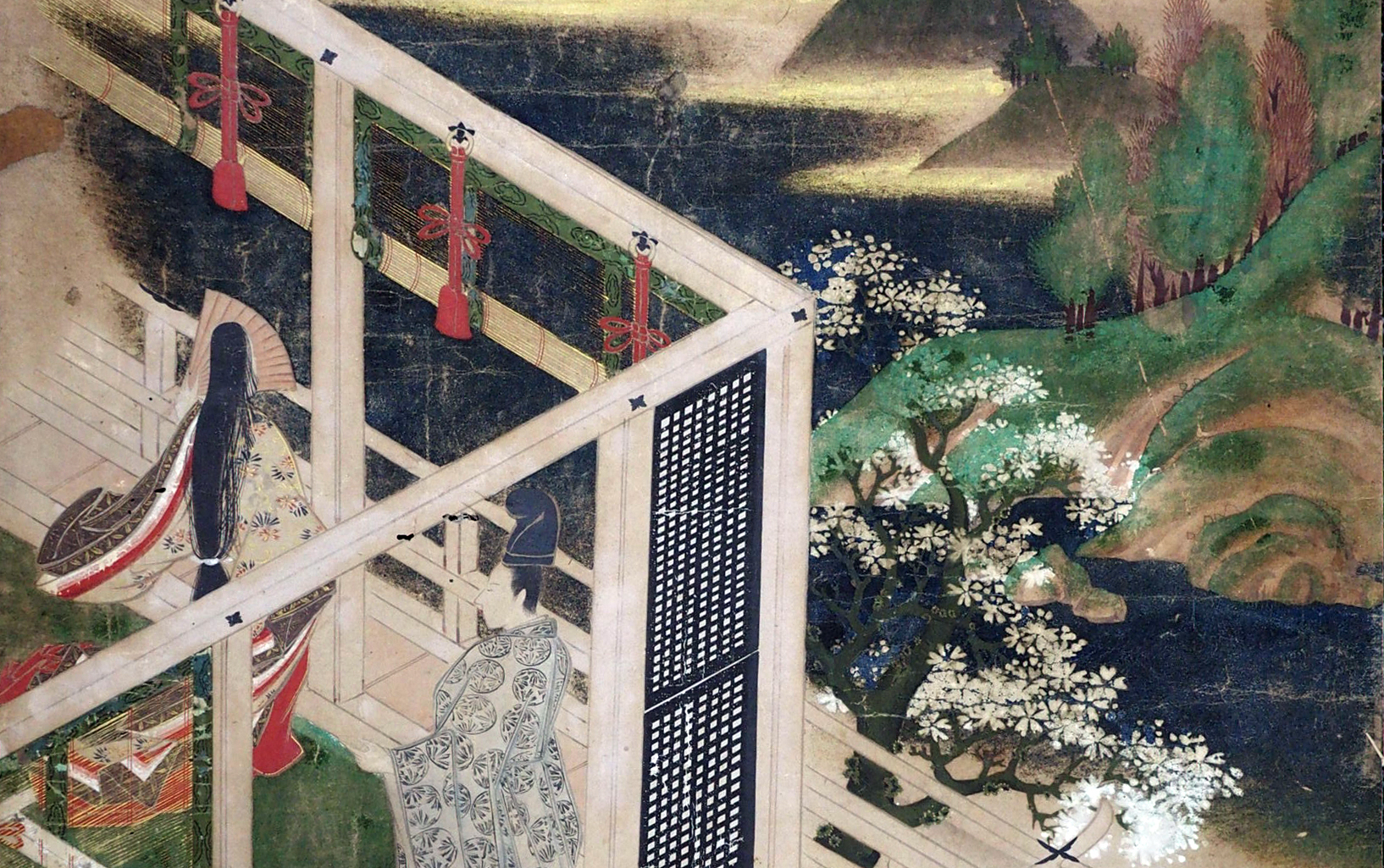などてか深く隠しき 夕顔12章03
原文 読み 意味
などてか 深く隠しきこえたまふことははべらむ いつのほどにてかは 何ならぬ御名のりを聞こえたまはむ 初めより あやしうおぼえぬさまなりし御ことなれば 『現ともおぼえずなむある』とのたまひて 『御名隠しも さばかりにこそは』と聞こえたまひながら 『なほざりにこそ 紛らはしたまふらめ』となむ 憂きことに思したりし と聞こゆれば
04143/難易度:☆☆☆
などてか ふかく/かくし/きこエ/たまふ/こと/は/はべら/む いつ/の/ほど/にて/か/は なに/なら/ぬ/おほむ-なのり/を/きこエ/たまは/む はじめ/より あやしう/おぼエ/ぬ/さま/なり/し/おほむ-こと/なれ/ば うつつ/と/も/おぼエ/ず/なむ/ある/と/のたまひ/て おほむ-な/がくし/も さばかり/に/こそ/は と/きこエ/たまひ/ながら なほざり/に/こそ/まぎらはし/たまふ/らめ と/なむ うき/こと/に/おぼし/たり/し と/きこゆれ/ば
「どうして特にお隠し申す必要がありましょう。ただ、あの場合、どういう機会に特別でもないお名前を申し上げられましょう。出会った当初より奇っ怪で思いもよらぬ形をとったご愛情でしたから、本当のことだとも思えない求愛だとおっしゃって、お名をお隠しなのも、それほどにまで愛してくださっている証拠だとご理解申しあげながらも、いい加減な気持ちだからこそ誤魔化しになるのだろうと、まあそのように、お名前をお告げにならないのを心苦しく思っておいででした」 と申し上げると、
などてか 深く隠しきこえたまふことははべらむ いつのほどにてかは 何ならぬ御名のりを聞こえたまはむ 初めより あやしうおぼえぬさまなりし御ことなれば 『現ともおぼえずなむある』とのたまひて 『御名隠しも さばかりにこそは』と聞こえたまひながら 『なほざりにこそ 紛らはしたまふらめ』となむ 憂きことに思したりし と聞こゆれば
大構造と係り受け
古語探訪
いつのほどにてかは何ならぬ御名のりを聞こえたまはむ 04143
あっという間にすぎてしまったため、名乗る時間がなかったする注があるが、時間の短さが問題なのではない。右近にすれば、あなたが名のられないのに、どうして名乗る機会があったでしょうと反論しているのだ。お互い相手のせいにしているので、光は「あいなかりける心比べどもかな/04144(無意味な意地の張り合いをしたものだ)」と感想をのべるのだ。時間が短いことが原因で名乗れなかっただけなら、こんな感想は出ない。「何ならぬ御名のり」について、つまらぬ名前をなのるではない。この「何」は、何か特別の、特に言っておくべきなどの意味。何ならぬ、特別なものでもないの意味。つまらないではない。
初めよりあやしうおぼえぬさまなりし御こと 04143
「さまを変へ 顔をもほの見せたまはず 夜深きほどに 人をしづめて出で入りなどしたまへば 昔ありけむものの変化めきて うたて思ひ嘆かるれど/04051」を受ける。「昔ありけむものの変化」は山の神(蛇)が姿を隠し女のもとへ通ったという三輪伝説(古事記・日本書紀)などが下敷きであろうとされている。物の変化とも思えるような異常な恋愛だったのである。光は遊戯としてこの恋愛を愉しんでいたが、女の方では少なくともその当初は恐怖の体験であったのである。男の見る目と女の見る目の違いをこれほど闡明にした文章は、古今にないといっていいかもしれない。恐怖の中にエクスタシーがあったか否かは想像するしかない。
現ともおぼえず 04143
三輪伝説にあるような恋愛であり、それほど楽しかったのではなく、それほど恐ろしかったのである。
のたまひて 04143
「御名隠し……たまふらめとなん」を飛び越えて、「憂きことに思したりし」にかかる。
御名隠しもさばかりにこそは 04143
「さばかり」を光の君であろうからと解する注がある。夕顔は最初、光とは思っていなかったことは、これまで繰り返した。それとは別に、『注釈』のとおり、「さ」は指す言葉が前にある指示語であり(前世の縁など常套句として指示する語が前にない場合があるが、常套句以外を受けることはない)、光の君を指す用法はない。かと言って、『注釈』のように、直前の「御名隠し」を受けるとするのも誤りである。そもそも「……こそは」は、~であるためだと後から理由を示す表現である。もとは「さばかりにこそは御名隠しも(あらめ)」という文が倒置されてできたのである。「さばかり」だからこそ名を隠されるのだろう、との文である。名を隠されるから隠されるでは意味がないのである。では、「さばかりに」は何を受けるのか。いろいろ受けられそうで、何を受けるのかはっきりしない。そういう場合はどうするか。Xとして保留し、残りを考えるのである。
聞こえたまひながら 04143
「聞こえたまひ」は問題のある個所だが、それは後回し。「ながら」は逆接をつくる。「なほざりにこそは紛らはしたまふらめ」は、本気でないからお紛らわしになるのだろうの意味。「ながら」が逆接で、その後が「本気でないから」とくれば、「ながら」の上は、本気だからという意味のことがくると推測できる。答えは出た。光の前言「さばかりに思ふを知らで」の「さばかりに(思ふ)」がと同じ用法。さばかりに思ふは、一種の常套句だから、光の前言を受けたというより、光の言葉が前言を受けずに常套句として文脈よりわかると同様の用法で、ここも文脈より明らかな常套句用法なのだ(文脈より明らかでないと感じるのは、現代人が読解力をなくしたからであって、紫式部のせいではない)。
整理すると、相手様が名をお隠しになるのも、とても愛していらっしゃるからだともご理解申しあげながら、それでも、(実は)本気でないからごまかしになられるのだろうと……。「聞こえたまひながら」の「聞こえ」は(夕顔が光に)言うの謙譲語だが、それを右近が使うのは無理があると昔から考えられてきた、とのことであり(『注釈』)、そういう注意を促す注釈が多いが、「言ふ」の謙譲語だと考えるからおかしくなるのだ。ここは名のらぬ光の態度を愛すればこそと「理解する」という意味。解釈のしこそないが、文法をもゆがめてしまうのである。「憂きことに」:結局、夕顔は、はじめから、物の変化のようにおびえ、愛されているからと頭で理解しながら気持ちは晴れずにきたというのだから、物の怪に取り殺されたというより、光の恋愛のし方に耐えられなかったせいかとも思われる。少なくとも、死の原因の一部は、光がずいぶん夕顔の恐怖心を煽ったせいであるに違いない。
なお、「さばかりにこそはと聞こえたまひながら」について、上にように「聞こえ」を「言ふ」でなく「思ふ」の謙譲語ととらえるならば、「さばかりに」は常套句用法と考えず、光の言葉を右近がまるまる繰り返し、そうご理解申し上げていた、のように右近が夕顔の立場になって発言したと考えることもできる。