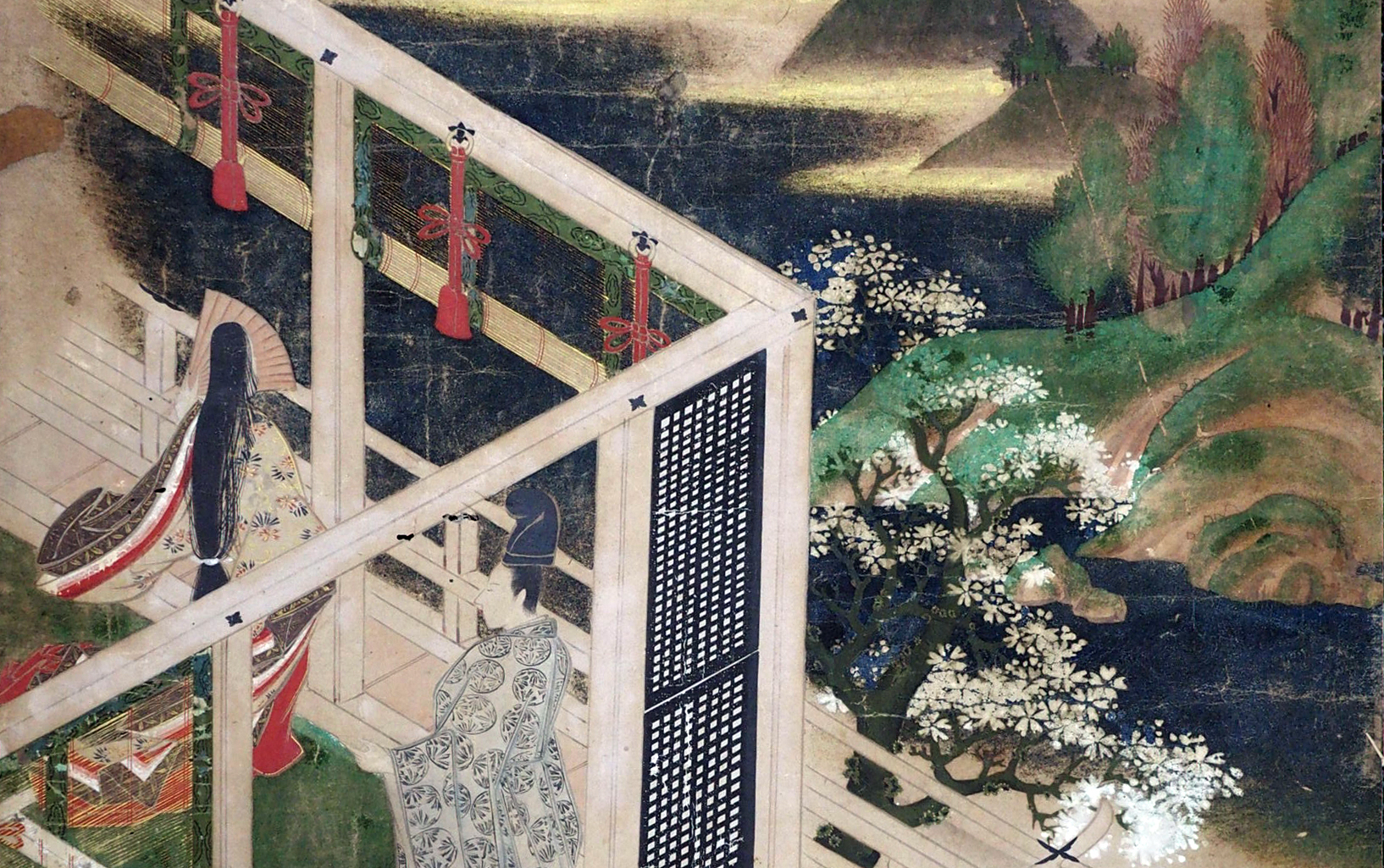こはぎがうへぞしづこころなき 小萩がうへぞ静心なき 小萩がうえぞ静心なき こはぎがうへぞしづこころなし 小萩がうへぞ静心なし 小萩がうえぞ静心なし 01-086
小萩の身の上が心配だと解釈されているが、それでは、なぜ「などやうに乱りがはしき」なのか、また、「いとかうしも見えじと思し静むれど/01-087」以下の叙述の意味が不明になる。帝は「いとかうしも見えじ(静心なきとは見られまい)」と自制しようとした(「思し静むれど」)、すこしもがまんできなかった(「さらにえ忍びあへさせたまはず」)とつづく。「静心なき」は、文章の論理展開としては帝に対して用いられているのである。「小萩がうへ」は小萩の身の上の意味は当然として、小萩の父帝(上=帝)の二つの意味を兼ねていると考えるしかないのだ。帝は愛妻を失い、政治をも疎かにして国を危うい方向に向かわせているのだ。そうした帝批判を含むために「乱りがはしき」(不遜)であるが、「心をさめざりけるほどと」(娘を失って冷静さをうしなっている時期だから)、お許しになったのだろう「御覧じ許すべし」。
そもそも「静心なき」は「心をさめむ方なきに」という命婦が帝の言葉として引用した言葉を、さらに援用したものであろう。母と命婦の立ち場の違いが最も闡明になる、この場面のハイライト。「身に余るまでの御心ざしの、よろづにかたじけなきに、人げなき恥を隠しつつ交じらひたまふめりつるを、人の嫉み深く積もり、安からぬこと多くなり添ひはべりつるに、横様なるやうにて、つひにかくなりはべりぬれば、かへりてはつらくなむ、かしこき御心ざしを思ひたまへられはべる/01-070」と母が帝の寵愛をなじったのに対して、命婦が「世にいささかも人の心を曲げたることはあらじと思ふを、ただこの人のゆゑにて、あまたさるまじき人の恨みを負ひし果て果ては、かううち捨てられて、心をさめむ方なきに、いとど人悪ろうかたくなになり果つる/01-073」と帝のせいではなく、前世の定めだったのだと、命婦が切り返した言葉の中に出てくる。母が恨みは並大抵ではない。
荒き風 ふせぎし蔭の枯れしより 小萩がうへぞ静心なき
などやうに乱りがはしきを 心をさめざりけるほどと御覧じ許すべし
表の歌意:強風をふせいでくれた木が枯れたのでそれ以来、小萩の身の上が心配でなりません。どうか若宮のことをお願いします。
裏の歌意:宮中を揺るがす嵐で娘が亡くなってからというもの帝は平静さを失ってしまわれた、どうか若宮のことをもっと気にかけて下さい。
などと不謹慎な詠みぶりに、気持ちが収まらない折りだからと帝は大目に見ておいでのようでした。