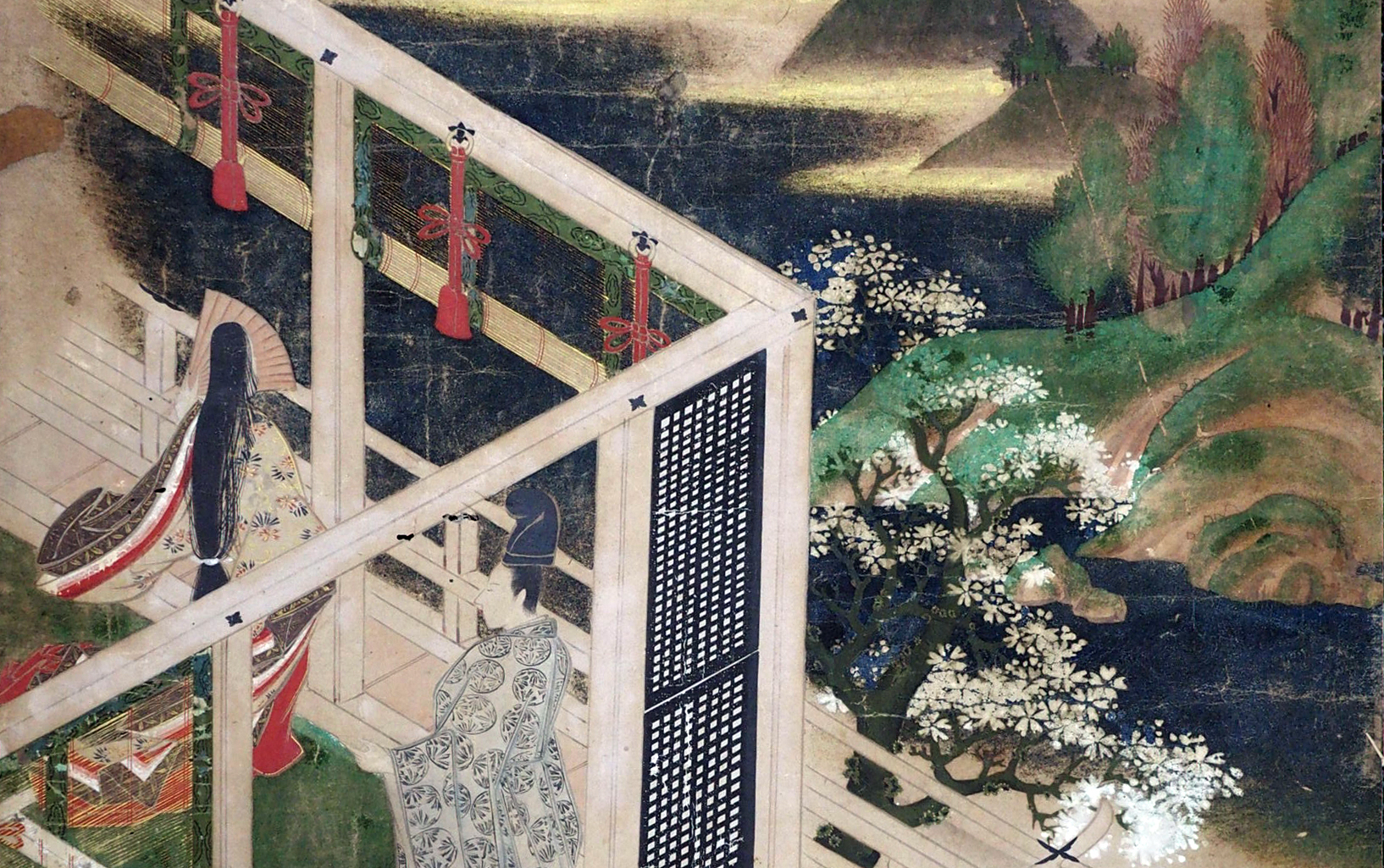いづれの御時の物語 ―護月―
初回 ヒロと別れ、源氏物語を教えるはめになる
二月最後の金曜日、日が少し傾き始めていた。突然、机が振動で細かく揺れ、携帯電話がブザー音を発しながら踊り出した。ヒロ? 数ヶ月前に出て行った彼女の顔が浮かんだ。わけないか…。携帯を裏返すと、〈ミサキ〉の文字。姪からの呼び出しに、つい顔をしかめる。すぐに出ないとやっかいだとは思いながら、出る気が起きない。三度目のベルが鳴り終わり、静寂が訪れると、部屋の空気が張り詰め、思わず携帯に手が伸びた。
「ごめん、トイレに行っていて」
「そう」の一言。そんな言い訳が通用する相手じゃない。
「でさぁ、お願いがあるの」
ミサキは怒るどころか、いつにない甘え声。胸がさわいだ。日曜の今日で、何の願いができるのだ! ミサキに振り回された一日が、まざまざと思い出された。
「友達の誕生日会に着て行く服がないの」
発端は電話の一言だった。かあさんに言えよ、なんでこっちに持ってくる。渋谷で一軒ブティックを見て、茶だろ。茶ぐらい出す気でいたからいいとして、もう一軒お願いって。今考えれば、それが全ての始まりだった。渋谷に店はいくらでもあるのに、池袋の雑居ビルに連れ込まれ、散々待たされた挙げ句、どっちもいいわねって、喫茶店で謎の微笑を浮かべながら。その微笑みに、危険を知らせるセンサーは麻痺してしまったらしい。
「あと一軒、見るだけだからね。気にせん気にせん」
〈キニセン〉が、耳にこびりついて離れない。何で関西弁なんだ。あとで振り返れば、どうでもいいことだった。しかし、この時には、そのことばかりが気になり、まるで木偶の坊だ。どのルートで日本橋まで出たのか、三越に入った気がするが、どの店でどんな服を試着したのか、メモリーは保存されないまま電源off。
「大人な街はいいわね」
〈大人な街?〉おかしな日本語がスイッチとなって、再び脳が作動し始めた。白いテーブル越しに、携帯電話を切るミサキの様子を目で追っていると、パフェとコーヒーが運ばれてきた。
「今から行くのも嫌でしょ。取り寄せといたから安心して。ほんと、今日はありがとう。お礼にと言いたいけど、さすがに千疋屋は、高校性にはハードル高すぎね」
千疋屋だって? ようやく話が飲み込めてきた。よくも抜け抜けと言えたものだと、思ったが、願いの行方を確かめるのが先決だ。五万と三万と…。最後のは一番高かったけど、見るだけって言っていたからいいとして…。
「で、どれにしたの」
「やだ、言ったじゃない。決められないって」
「取り寄せたって言っていたじゃないか」
「だからね、そう言うことよ。もう何なのよ。大きな声出さないで。人が見るわ」
「え、じゃあ、五万と三万?」みるみる血の気が引いた。
ミサキは面白そうに、三本立てた指を、優雅に上下に振った。
「迷ったらぜんぶ買うものよ。気にせん気にせん」
ミサキは、よく熟したメロンのかけらを健康そうな赤い口に運び入れた。ぼくは手つかずのコーヒーを見つめることしかできなかった。不条理と怒りと、整理できないもろもろの感情で、頭の中はパンク寸前。〈気にせん〉そう、気にしちゃいけない。気にしたとたんに爆発だ。危ない、危ない、身が持たない。二度と〈お願い〉には関わるまいと決意した。
気がつくと、電話口からミサキの声が消えていた。日曜のことで怒りを新たにしているうちはよかったが、無言を相手にしている間に、不安がふくれあがる。やばいぞ、これは…。経験上、沈黙の長さと〈お願い〉の大きさは比例した。それを成し遂げるために払う労力や支出となると、もう計算すらできない。お手上げだった。
「あ、ごめん。待った?」
携帯は耳に当てたままなのに声が届かない。鼓膜は音を拾うが、言葉に変換されない。
「言わなかった? スパゲッティーゆで上がったから、作っていたの。ねえ、聞いている? 冷めるとまずいから、食べながらだけど、あの…兄さん、プロでしょ? 古文教えるの。教え方うまいらしいって、かあさんほめていたわ。いつも悪口しか言わないのにね、あっ、けなしたわけじゃないよ。教え方うまいっていうのは本当だろうなって、それが言いたかったの。そりゃ、兄さんの塾に行けばいいんだけど、かあさん嫌がるし。兄さんだってやりにくいでしょ、わたしが習いに行ったら。だから、お金はないの、わかるでしょ…」
〈カネ〉という音が、池袋で麻痺したきりになっていた防衛本能を呼び覚ます。
「金? いらない。後が怖いよ。いや、どうせ、かあさんには内緒だろ?」
今回は、どうやらこっちの土俵で相撲が取れそうだ。そう思うと、力がわいてきた。
「だから、兄さん好きよ、わかりがよくて」言いながら、ミサキは楽しそうに笑っている。
「で、何を教わりたいの?」
「源氏物語の冒頭。姉さんが出てった日のこと覚えている? あの時の説明、よくわからなかったから、聞き直したいの」
ヒロと別れた日のことが蘇る。ぼくは天を仰いだ。
源氏物語は大学時代から興味があった。元は、小説を書く手本になればとの思いからで、現代語にはない息の長さ、話し言葉でありながら文章語に特有な骨格を学ぶには、源氏物語はもってこい。納得できる解釈を考えることが楽しかったから、読むと言うより謎解きに終始した。先に進むことが目的ではなかったから、興味が引く表現を繰り返し写し、朗唱した。それでも五年ほどかけ、第五帖の『若紫』に取りかかる頃、春先で、桜が咲き始めていた。姉が、両親の反対を押し切り、今の夫の後添えに納まった。四月から小学校にあがるミサキは夫の連れ子で、実母を早く事故で亡くしていた。若紫になぞらえるわけではないが、ぼくはミサキをかわいがった。その頃から、源氏に没入することができなくなった。幾度か思い直し、始めから読み直すが、出だしも出だし〈いづれの御時にか〉でつまずいてしまう。それまで〈どの帝のご時世であったか〉と訳してきたが、帝は桐壺更衣を愛した、光源氏の父である。どの帝という問は変じゃないか、ふと浮かんだ疑問が解けない。醍醐天皇の時代をほのめかすなどの注釈はあるが、これから物語を始めようという時に、物語から注意を背けたりするだろうか。答えはすぐに見つかるものと思ったが、いくら考えても答えは出なかった。謎は謎のまま夾雑物として残り、以前のようにのめり込むことはできなくなった。しかし、解けないことが、源氏物語を一層魅力あるものにした。浸ることはかなわなかったが、切れると途端に禁断症状が現れる。源氏は今や麻薬となった。
ヒロは塾の最初の教え子で、ぼくが小説を書くのを喜んだ。そのため、文章修行として源氏に熱を上げることに、当初は進んで理解を示したが、同棲を始めて数年、ヒロが二十代、ぼくが三十代を折り返す頃から、源氏はいさかいの種となり出した。物書きを目指すなら、まずは作品に向かうべきだ。物書きを諦めるなら、塾講師に専念すべき。暮らしは実質、会計士であるヒロが支えたから、言い返すことはできなかった。それでも、ヒロはぼくを理解しようと努力した。源氏のどこがそんなに面白いのか、たびたび聞かれた。喉に引っかかった謎のせいで、源氏はもう語る対象ではなかった。小説を書くことにも興味は失せた。生活を支えてもらっていた負い目もあって、源氏に関して触れられることを頑なに拒んだが、もう潮時だと、自分でも感じていた。
去年の大晦日。いつもの悶着が始まったが、終わり方はいつもと違った。
「このままじゃ結婚もできない。子供も産めない」と、ヒロは最後に泣きじゃくった。
前日、ヒロは何時間も実母と電話をしていた。別れ話が出てもおかしくない状況だった。
「ごめんよ、ぼくが悪かった。わかったから、もう泣かないで。春から塾のコマ数を増やすことで、塾長に話はついている。ちゃんと働くから」
「小説も書いて。ね、それはやめてほしくない」
「書く気になればそうする。でも、まずはお金を貯めないと。挙式の費用が貯まったら、おかあさんに会いに行こう。それまで源氏は封印するよ。だから、つらい思いをさせたことは勘弁してほしい」
出任せを言ったわけじゃない。これまで切り出すタイミングがなかっただけだ。
年が改まり、その二日目だった。突然だった。前触れもなく、謎を解くカギが脳天を直撃した。何だ、答えは出ていたのか! 夢中でトイレから飛び出し、書棚に駆け寄ると、
「何、その恰好!」
後ろから呼び止める声。ミサキだった。
「来ていたの? ヒロは?」
ミサキは答えるどころか、ぼくを指さしげらげら笑った。苦しそうに顔をゆがめ、〈おも・らし・でも・した・の〉と、ようやくに言い終えた。足もとにズボンがずり落ち、ぼくはパンツ姿で立っていた。頭が真っ白になった。
「初詣行こうって、姉さんから電話もらって。源氏ばかり読んでないで、一緒に行こうよ」
ぼくは、手にしたばかりのカギで、謎が解けるのか試してみたくて仕方がなかった。形ばかりミサキに説明しながら、夢中で源氏に向かっていた。
「源氏!」
ヒロが立っていた。みるみる形相が変わった。足もとには、コンビニの袋からハーゲンダッツが転がり落ちている。机から源氏をむしりとり、床にたたきつけた。その荒立ちに事の重大さがわかり始めた。
「聞いてよ。解けたんだ」
ぼくの言葉を掌で制し、「もう無理」そう言い残して、ヒロは出て行った。
ぼくは呼び止めることさえできなかった。十年この方考え続けた謎の重み、それがあっさりと氷解した今の喜びを、源氏を呪う相手にどう伝えればよいのか。日頃から源氏を共有してこなかったことが悔やまれた。一方で、十年という年の差が、いつになく身に染みた。もうヒロも若くない。こっちも中年、これ以上引き留める方が酷だ。すでに天秤は大きく傾いていた。バランスを元に戻す値打ちが、自分の中にあるとは思えなかった。
「前にはずっと、源氏の注釈やっていたのでしょ。姉さん、いつも尊敬していたわ。だから、わたしも知りたいの」
源氏の冒頭が、別れるきっかけになったことをミサキも知っている。知った上で望むからには、思うところがあるのだろう。だが、別れの場面に立ち返る勇気はなかった。
「ごめんよ、説明する自信がない」
その時だった。ヒロがぼくをにらむ気がした。
「難しくて、高校生にはわかりっこない?」
「そんなことはないけど…」
言葉を濁すと、さらにヒロの目つきが鋭くなった。代わりにミサキに説明してやれば、ヒロも喜ぶかもしれない、ふとそんな気がした。
「うまくできるかわからないけど、時間をかけていいなら、やってみようか」
明日の一時に部屋に来るように言って、電話を切った。塾長からLINEが入っていた。
――週明けより全国学校閉鎖決定。春期講習は中止に。今後の予定はまた連絡
新型ウィルス感染拡大防止のために、学校閉鎖は予想されていたものの、もう少し先の話だと思っていた。すぐに塾長に電話をかけたがつながらない。塾にも携帯にも連絡したがだめだった。〈電話下さい〉とLINEしたが、結局、その日は連絡がなかった。塾の経理を続けているヒロにも情報は回っているはずだが、LINEをチェックした形跡はなかった。
二回 論理は不変、意味は心変わり
原文一 冒頭一文の全文
いづれの御時にか、女御・更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり
ぼくはA4用紙に、大島本の原文を書き写しておいた。
「これが原文。〈さぶらふ〉や〈たまふ〉、それに〈なか〉も、漢字を当てる教科書が多い」そう言いながら、〈候ふ〉〈給ふ〉を隅に書き足し、「原文と言っても、紫式部が書いたオリジナルは、現存が確認されていない」と、説明した。
「現存がなんちゃらって、まどろっこしい言い方ね。それって〈ない〉とイコールなわけ?」
「最初から攻めてくるねえ。残念ながらイコールではない。もしかしたら、今もどこかに眠っていて、ひょっこり明日、出てくるかも知れない。だから、現時点では、まだ存在が確認されていない、という言い方をする。今知られている中で、オリジナルにもっとも近いとされているのが、この〈大島本〉と言われる写本。藤原定家が校訂した青表紙本という系統で…」
「たしかニュースになったわ」
「『若紫』という五冊目の定家自筆本が見つかった。元からの四帖は、重要文化財だ」
そう言って、新聞の切り抜きを見せた。
「どう、教科書で見るのとはずいぶん違うだろ」
「万葉仮名って言うの、このにょろにょろのやつ」
「変体仮名ね。現在の活字とはずいぶん違う。今のひらがなは、一つの音に対して表記はだいたい一つだけど、変体仮名は、例えば〈あ〉なら、安全の〈安〉や阿倍の〈阿〉など四つ五つの表記法がある。文字以外に気づくことは?」
「そうね、ずらずらって書かれていて、読むのが大変そう」
「そう、句読点がない。あまり漢字を使わないのも特徴だ。数字など頻出する漢語以外はひらがなで書く。数百くらいくずし方を覚えたら、原則、王朝文学は読める。実際は、書き癖があって、そうもいかないけどね。ひらがなだけだと読みにくいので、教科書などは適宜漢字を交ぜる」
「でも、〈候ふ〉、漢字を読む方が難しいけど」とミサキが笑った。
「全くだ」と、ぼくは笑いながら、
「わかりにくい所はあるかい?」と質問した。
○訳文:それほど高貴な身分ではない方で、特に寵愛を受けていらっしゃる方がいた。
ミサキはガイドの訳を読み上げた後で、
「わかれって方が、無理じゃない?」と、口をとがらせた。
ぼくが相づちを打ちかねていると、
「それ程ってどれ程よって、聞きたくなるわけ。それに、〈何々ではない方で、これこれする方がいた〉なんて日本語、使う人いる?」と、逆に質問してきた。
「なるほど、なるほど。いいセンスしているじゃないか」
「それってひやかし? けなし?」
「ほめてるんだよ」と言うと、「でしょ? でしょ?」と、うれしそうに同意を求めた。
「わからない所が二点だね。同時に考えるのは大変だから、一つずつやろう。〈いと〉が問題になっているけど、調べた?」
「とてもという意味と、打消と一緒になって、それほど・たいして…ないという意味が出ていたわ」
原文二 「いと」の係る先
いとやむごとなき際にはあらぬ(が…)
意味一
いと→やむごとなし(き):たいそう… 強調
意味二
いと→…あらず(ぬ):たいして…ない 陳述の副詞
ぼくは上のようにまとめた後で、
「どっちだろう?」と、質問をした。
「〈ぬ〉は、元が〈ず〉で打消でしょ。だから、二の意味だわ。訳もそうなっているし」
「源氏物語の冒頭は、古文の中でも最も有名な文章だろ? だから、この文に現れる語彙や文法を、多くの辞書が例文として採用する。〈いと〉も例外ではない」
「じゃあ、いくつか辞書を引いて、よさそうなのを探せばいいの?」
「正解はどこにもない。自分で納得できたものだけが答えだ。それがここでのルール。いいかな?」
「きのう、時間かかるって言っていたのは、そういうことね」
「そう。〈いと〉の検討の前に、単語の意味を確認しておこう。〈やむごとなし〉は、止むことがないが短縮したと言われている。この上なく高い、でいいだろう。〈際〉は、際立つと、今も使うように、二つ並べるとその境目がはっきり区別できるイメージ。合わせて、この上なく高い身分、となる。関連するから〈女御〉〈更衣〉もやっておこう。どう?」
「女御は大臣の娘で、更衣は一般の貴族の娘でしょう」
「はっきりした区別があるってところがポイントだね。三位以上の公卿の娘が女御で、四位五位クラスの殿上人の娘が更衣とされている。時代によって変わるから、ざっくりした理解でいいと思うが、女御の父は、大臣として政治の中心にいる。天皇にしてもないがしろにできない。桐壺更衣の父は大納言だ。大納言は大臣に次ぐ地位で、トップクラスの貴族が独占した。ただし、出世コースにありながら、大臣になれずに亡くなった点が重要だ。娘としては、もう一度家を盛り立てたいと思うだろう。こうして宮仕えが宿願となる。だが、女御と更衣の身分差は、いろいろな面で現れる。女御は、初夜を開けた際に宣旨を受ける。正式な手続きを経た公的な身分だ。一方、更衣はもともと天皇の衣服の着脱を手伝う女官に過ぎない。スタートラインが違う。中でも、皇后という天皇の正妻選びに一番の違いが現れる。女御は皇后になれるが、更衣はなれない。本来、皇后は、内親王という皇室の血を引く女性のみに許された。臣下では、藤原不比等の娘の光明子が初めて皇后になった。以後、女御から皇后になるコースを藤原氏が独占する。こうした背景の中で、この帝は桐壺更衣を溺愛する」
背景知識
女御:三位以上の大臣の娘 公的存在 皇后になれる
更衣:四位五位の貴族の娘 私的存在 皇后になれない
「暗雲漂う感じね。危険な恋愛の匂いがする」
「恋愛かどうかは留保がいる。後宮女性は、まずもって性の対象だ。現代のような恋愛は、男女平等の上に成り立つ。とはいえ、死ぬ時は一緒だと誓い合った仲なのだから、精神面では現代の恋愛に近いものがあったのだろう。もちろん、帝のそんな個人的な感情が、許される時代ではない。ここで、少し人間関係を整理しておこう。右大臣の娘、弘徽殿の女御が第一夫人として長子をもうけている。この二人が、皇后・皇太子のナンバーワン候補だ」
「候補ということは、まだ決定じゃないのね」
「医療も未発達であり、呪いが横行、天災も多発。第一子が今健康だからと言って、何が起こるか知れたものじゃない。だから、正式な冊立はすぐに行われない。リスク回避には、子をたくさんもうけ、育てておく必要がある。そこに後宮制度の意義がある。それはさておき、〈いと〉だけど、〈は〉の有る無しで意味の違いが出てくる。どうかな?」
ミサキはしばらく考えた後で、
「〈は〉なしだと、単純にそういう位じゃないと否定しているだけだけど、〈は〉が入ると、位ではないなら、どういう位なのかって、知りたくなるわ」
「Good job!」と、ぼくは笑った。
○際にあらず:位じゃない
○際にはあらず:位ではなくて…
「その違いがわかるなら、一気に攻めよう。〈いとやむごとなき〉位じゃないなら、どういう位なのか。どう?」
ミサキはしばらく原文を見つめていたが、首を振った。
「答えは、この文章の後に出てくるから、先を読む必要があるのだけど」
「えっ、何それ、意地悪? なんかの仕返し?」ぼくをにらみながら、ミサキは笑った。
「誰もが知っている有名箇所だったよね。だから知識として知っていてもいい、そう思って聞いたわけ。じゃあ、質問を変えよう。この文の話題は誰?」
「桐壺更衣に決まっているじゃない」
「じゃあ、〈時めきたまふ〉の主語は?」
「同じじゃないの?」
「桐壺更衣だよね。では、もう一度聞く。〈いとやむごとなき際〉って、実質、どんな位? どういう位じゃなくて更衣だって言っているの?」
「女御じゃなくて更衣なのはわかるけど…そうか、〈いとやむごとなき際〉の実質は女御のことで、そうではない更衣風情がってことか。ふんふん、わかる、わかる」
「〈いとやむごとなき際〉と〈女御〉がイコールなら、〈いと〉はどこに係るか」
「女御が〈いとやむごとなき際〉なんだから、やむごとなしに係るしかない。なるほどね」
「それが論理的帰結だ」
「論理的って、古文と論理、あんまり結びつかないなあ」
「じゃあ、聞くけど、王朝人と現代人と共通点はどこかな」
「なんで兄さんと話していると、いつもそもそも論になるかな」ぶつぶつ言いながら、
「そりゃあ、いろいろあるけど、大きく言えば、人間ってことじゃない」と舌を出した。
今日、ぼくが一番伝えたかったこと
「そう、人間だから言葉を使う。言葉は、そこに込められた意味や感情は、時代により変化しうる。それでも、ぼくたちがそれを理解できるのは、今も昔も論理が変わらないからだ。だから論理を駆使しないといけない。でないと、変化に気づかず足をすくわれる」
昼をかなり回っていた。とにかく空腹でたまらない。近くのコンビニに弁当を買いに出た。戻る途中で携帯が鳴った。塾長からだった。
「携帯なくしてな。いろいろ心配させたな。古川くんのこと覚えているか? 電通大に行った。そう、ヒロの同級生。ホームページの作り直しを頼んでいて、今はホテル。明日は戻るから、夕方、遅い方がいいな。いろいろと相談したいから塾に来てくれ」
一人でまくし立てて電話は切れた。初めに行動ありきの人だから、いろいろと動いているのだろう。ミサキもちょうど電話をしていた。
「一緒に聞きたいって子がいるの、呼んでいい?」
「これから? 今日は疲れたよ。明日にしないか?」
一人よりいろいろ質問が出る方がありがたいが、塾のことで安心したら、力が抜けてしまった。ミサキもうなずいた。
「論理が大事だって話だから、一番数学できる子呼んだわ。ヒロっていうのよ」
別れた彼女と同じ名を口にした。目がくらむ思いがした。
「どんな子か楽しみだな」動揺を隠そうと、心にもないことを言ったが、後悔した。
三回 名前の入れ替えと別れの再現、さらば同格よ
日曜の朝、玄関を開ける音。つづいて、
「ちょっとコンビニ寄って来るから、先に上がって」と、ミサキの声。
ヒロは玄関先で身じろぎ一つせずに待っている様子。十時になった。靴を脱ぐ音。時間を調整していたらしい。生真面目な高校生を想像したが、
「ちわっ」と、部屋に上がって来たのは、無精ひげを生やした茶髪の若者だった。
魂消ると同時に笑いがこみ上げてきた。そりゃそうだ、ヒロにもいろいろあっていい。ふと、誕生日の友達というのは、こいつのことかと思うとムカムカしてきた。あらためてヒロを見る。
「ちわっす」と、再び会釈してきたその態度は、なかなか挑戦的だった。
そこへミサキが戻って来た。
「アイス、買いに行っていたの。三分遅れね」
「四分四十四秒、この時計だと」と、ヒロが置き時計を指さした。
なかなか面白い関係だなと興味がわいた。ミサキがコンビニの袋から取り出したのは、ヒロが家を出た時と同じ、ハーゲンダッツだった。
「前に食べそびれたでしょ。これ食べたかったの。なかなか評判いいのよ」
当てつけているのは明白だった。何の狙いがあるのか。ぼくは、黙って台所に立ち、しばらく呼吸を整えた後、コーヒーを入れて部屋に戻った。
「食べないの?」
「最近、太り気味でね」
食べたくない旨だけは伝えておこうと思った。
「ちゃんと料理しないとね」と、顔を上げないでミサキが言った。
ぼくは黙ってうなずき、厚手のカップを両手で包み込んだ。コーヒーの熱を感じてはカップを掌の中で動かした。アイスを食べる音だけが部屋を満たした。
原文三 きのうのおさらい
いとやむごとなき際にはあらぬ
二人がアイスを食べ終わる頃を見計らって、
「まずは昨日のおさらい。この文の話題は桐壺更衣。更衣は女御より格下で、扱いは階級に準じるのがこの時代のルール。〈いとやむごとなき際〉は、実質〈女御〉であり、〈いと〉は、〈やむごとなし〉に掛けて読むのが正しい。で、今日は〈が〉がテーマだけど」
いつになく早口になっていた。「何だか、学校の先生みたい」という、ミサキの感想もわからないでもない。
「つまり、更衣は〈やむごとなき際〉ってことか」と、ヒロがつぶやいた。
ぼくは、よくのみこめず、「どういうこと?」と、説明を求めた。
「ここに出て来るランクは、一番女御、二番が更衣。今、〈女御〉を表すのに〈やむごとなき際〉では不足で〈いと〉を加えた。つまり〈やむごとなき際〉単独では、二番以下の階級しか表せない。ここで二番以下を表す表現は、更衣以外にない。以上」
「すごい、すごい」と、ミサキが感心した。
「まさに論理の力だね。今の等式を使うと、〈いと〉が〈たいして…でない〉という陳述の副詞ではないことが証明できる」
「たいして高貴ではない位って訳のことね」と、ミサキが補った。
「そう。ヒロくんが教えてくれた等式は〈更衣=やむごとなき際〉だね。〈いと〉がないから最上級とは言えないまでも、〈やむごとなき際〉ではある。つまり、相当高貴な階級だ。一方、たいして高貴ではないという訳では、中程度かそれ以下の階級になってしまう。帝の性の相手だから、高貴であるには違いない。従って、この〈いと〉を打消と呼応する陳述の副詞と考えてはいけない」
ヒロは困った表情を浮かべながら、「ぼく…ヒロじゃなくてタカオです」とぽつり。
「えっ?」ヒロじゃない? それも驚きだったが、自分と同じ名前に二度驚く。
「いくら言ってもこいつは聞かないから、いいにしているけど、別の人から言われるのは」
ミサキは笑い転げている。これも企みあってのことに違いない。
「それはごめんよ。知らなかったから、許してね。実は、ぼくもタカオって言うんだ」
「そうなんですか」その驚きには不自然さがあったが、気づかない振りをした。
「ちょっと呼びにくいけど、タカオくんは、古文はどうなの。好きかい」
「君づけもなんだかなあ。それに先生も呼びにくいでしょ。ヒロでいいにするよ」
また振り出しか、勘弁してくれ。その時、ミサキが前に言った〈気にせん〉が頭の中で響いた。タカオだって本名だかどうだか、気にしたって仕方ない。ミサキはまだ面白そうに笑い転げていた。
原文四 準体言って何なの
いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり
ぼくは、改めて書いてから、「〈ぬが〉を説明してみて」と、ヒロに頼んだ。
「〈ぬ〉は準体言で、〈人〉の省略」と素っ気ない。こちらの力量をまだ疑っているようだ。
「ジュンサイ?」と、ミサキが口をはさんだ。
「体言に準じるから準体言。〈会うは別れの初めなり〉っていうだろ」
「変な例文ね」ミサキが突っ込みを入れる。
「〈会うは〉は、〈会うのは〉とか〈会うことは〉を縮めた形」と、ヒロが補った。
「古文ではいろんな用語が出てくるけど、一番大切なのが〈体言〉と〈用言〉。〈準体言〉は、体言と同じ働きをするのだから、体言がピンと来ないと話にならない」
「体言は名詞のことでしょ。そのくらいは大丈夫よ」と、ミサキが請け合った。
「念のため〈会うことは〉で説明しておく。この〈会う〉は、体言の〈こと〉につづくから連体形で、等式〈会うことは=会うは〉が成り立つ。これを一般化すると、〈連体形+体言=連体形(準体言)〉が成り立つ」
「準体言が、体言の働きをするってことはわかったけど、なんでわざわざ難しい名前をつけるの。質問、変かなあ」
「いや、とてもいい質問だ。わざわざ用語を作るのは、そこに着目してほしいからだ。準体言の大切さを知るには、体言の大切さを知らないといけない。体言の文中の働きは?」
「名詞でしょ、主語になる」
「そう、主語の代表選手の一番手は体言。それから忘れていけないのが、用言や助動詞が名詞の働きを兼ねる準体言」
「用言や助動詞が名詞の働きをするって、そんなのあった?」と、ミサキはポカンとする。
「準体言は名前に体言があるけど、連体形だから用言だ。用言のくせに体言の働き、即ち主語になる。この二重性がわかりづらい。だから用語を作って注意喚起する」
「英語の不定詞や動名詞みたいに思えばいいのね」
原文五 省略を補ってみる
いとやむごとなき際にはあらぬ〈人〉が、すぐれて時めきたまふありけり
「ヒロ説にならって〈ぬが〉の間に〈人〉を入れてみた」
「随分すっきりしたわね。〈人〉より上は済んでいるから、残るは後半ね。あら、どうしたの?」と、ミサキはヒロの顔をのぞきこんだ。
「それだと〈が〉は主格になる。同格のはずなのに」と、ヒロは頭をかく。
「同格って?」と、ミサキが聞く。
「〈何々する人で、これこれする人が〉って訳す決まりだけど、よくわからない」と、ヒロが答えた。
「じゃあ、同格とは何かを、次に考えてみよう。まずは、この文を二つに分けてみる。同格だから、二つある連体形の下に、同じ体言を補うのがミソだ」
●上の句:いとやむごとなき際にはあらぬ〈人〉が
●下の句:すぐれて時めきたまふ〈人〉
●述語:ありけり
今日の本丸:同格の定義
○同格のポイント一:上の句を、下の句が補足する
○同格のポイント二:上の句が格を決める、下の格は上と同じ
「同格のポイントは二点。下の句は上の句の補足説明で、文中の格は上の句が決める」
「格って?」と、ミサキ。
「主格とか目的格とかを決めるのは上の句。下の句の格は上と同じ。だから同格」
「下の格は上と同じ、それが名前の由来ね」と、ミサキ。
「下の句は同格で、上の格は主格でいいってことなのかな」と、ヒロがぽつりと言った。
「昨日も言ったけど、この文は非常に有名だ。だから、この〈が〉の説明はどの辞書にも出ている。しかし、同格の説明はなく、上の句と下の句を同格と説明するだけ。上の句は下の句と一緒、下の句は上の句と一緒、これだと、文中の格が決まらない。巨大なジンベイザメに小判ザメがくっつくから、行き先が決まる」
「今の説明だと、上の句が主で、下の句は添え物って感じだけど」と、ミサキ。
「下は補足に過ぎない。大事なのは上の句さ」
「上が格を決めるのだから、〈ありけり〉に対して主格。下は同じだから主格。でもそれで訳すと、下の方が大事な感じするけど」と、ヒロ。
「大事な点だから書き出そう。訳は考えやすくするために、単純化するよ」
論理的に考えるには単純化が大事!
●上の句:いとやむごとなき際にはあらぬ〈人〉が ありけり
●下の句:すぐれて時めきたまふ〈人〉 ありけり
「女御ではない人がいた。その人はとても帝から愛された。で、どっちの情報が重い?」
「これだと後ろの方がジンベイザメの気がする」と、ミサキ。
「ジンベイザメは比喩だから、文法用語にしないでね」と、おどけた後で、「実際、この文では、下の句の方が重く感じられる。同格説では、この点を説明できないんだ。続いて、同格の訳を検討しよう」
○上の句の訳:女御ではない人がいた
○下の句の訳:その人はとても帝から愛された
「二つを続けるとどうなるかな?」
「女御ではない人がいて、その人はとても帝から愛された。こんな感じね」
「これだと、〈ありけり〉は上にはついているけど、下にはついてないな。原文から少し離れている気がする」とヒロ横やりを入れた。
「じゃあ、やってみなよ」と、ミサキは口が悪くなる。
「女御ではない人がいて、とても帝から愛される人であった」
「〈人であった〉と〈人ありけり〉は離れているわね」と、ミサキもやり返す。
「では、辞書風の訳をつけてみよう」
「が」辞書風同格説の訳
女御ではない人で、とても帝から愛される人がいた
「〈で〉が現れた」と、ミサキとヒロ。
「こうして見ると、なかなか工夫はされている感じがするわ」とミサキ。
「でも、この訳だと、上が同格風で、下が格を決めている感じがする」
「Good job! 辞書は上と下が同格と説明するのに、訳は上が同格で下が格を決めている」
「結局、どっちよ、わけがわからない」と、ミサキが怒り出す。
「この〈が〉は、戦後もある時期までは、逆接を表す接続助詞と説明されてきた。訳せばこんな感じ」
「が」接続助詞説の訳
女御ではないけれど、とても帝から愛される人がいた
「とてもわかりやすいわね」と、ミサキは機嫌を直す。
「でも、ダメになった。〈が〉が接続助詞として使われ出すのは、源氏物語より一世紀ほど後の院政期からという論証が出て、この説はお蔵入りになった」
「いけているのに、残念だわ」
「代わって現れたのが同格説。注目すべきは、〈人がいた〉という部分。原文だと〈ありけり〉の主語に〈時めきたまふ人〉を立てている。推測だけど、同格説は、主語の立て方を接続助詞説から引き継いだ。繰り返しになるけど、この文は、古文で一番有名な文章だ。文学の写本で一番多いのが源氏であり、中でも一番多いのが桐壺だから、一番と断言できる。で、これまた推測だけど、院政期、つまり定家の時代、この文を書き写した人たちが、この〈が〉を接続助詞と読み間違えた。これを契機に接続助詞の用法が生まれて、固定化していった。それだけの力が、源氏の冒頭にはある。九百年間続いた〈ありけり〉の主語を、別の語に読み替えることができなかった。そこに同格説の無理がある」
「無理って」と、ミサキとヒロが声を揃えた。
「同格の代表は助詞の〈の〉だ。でも、上下二つも準体言なんて例はない。上には体言が書かれていて、下の準体言の後にそれを補うから、補足である同格が成立する」
「最初に聞いた、上が格を決め、下は補足という同格の説明と合致する」と、ヒロ。
「接続助詞で入っていた下の句の〈人〉を固定したまま、上にも同じ語を持ってきた。だから、どっちが同格で、どっちが補足説明かわからなくなったってわけね」と、ミサキ。
「そんなところだろう。あくまで推測だけどね。同格説が未だに採用され続ける力の源泉はどこかと考えると、根が深い気がする。さて、近年出版された文英堂の古語辞典には、〈が〉を同格とする用法は、この箇所以外になく、この例も主格を表す例と解釈できるため、同格の用法は認めない立場をとる、との説明がある。辞書でここまで明言することは、すごいことだよ。そこで、主格説を見ることにしよう」
原文六:白紙に戻って考える
いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり
「ゼロから再出発だ。この文全体の述語は何かな」
「〈時めきたまふ〉?」とミサキ
「〈ありけり〉じゃない?」とヒロ。
「じゃあ、それぞれの主語を言ってよ。ミサキちゃん、誰が時めくの?」
「桐壺更衣だけど」
「この文で言うと?」
「〈いとやむごとなき際にはあらぬ人〉だわ」
「いいねえ。じゃあ、ヒロ、〈ありけり〉の主語は?」
君づけしなかったことに、ヒロは一瞬戸惑いを見せたが、すぐに切り替えて説明を始めた。ぼくも胸をなでおろした。
「さっきから考えているけど…、見つからない。主語になるのは体言だよね」
「わたしのことを忘れてない? わたしは準体言よ」と、ミサキが笑いを取る。
「そうか。〈時めきたまふ〉が〈ありけり〉の主語か」
「〈時めきたまふ〉の下に体言を補うとして、〈人〉以外にないかな?」
「〈こと〉とか?」と、ヒロがぼくの顔を見た。
何となく信頼を勝ち得た気がした。
原文七:二つの準体言に別の語を補ってみる
いとやむごとなき際にはあらぬ〈人〉が、すぐれて時めきたまふ〈こと〉ありけり
「わかりやすくなったわ」とミサキ。ヒロもうなずく。
「〈人が〉を受けるのは〈ありけり〉じゃなく〈時めきたまふ〉。〈人が…時めきたまふ〉全体を省略した〈こと〉が受けて、〈ありけり〉がこれを受ける。訳はどうだい」
「が」主格説の訳
最上級の身分ではない人が、とても愛されることがあった
ミサキがつけた訳を、ぼくは書き留めた。
「ひっかかる所はどこにもない」と、ヒロも太鼓判を押す。
今日、ぼくが一番伝えたかったこと
「同格説と主格説の一番の違いは〈ありけり〉に対する主語の違いだ。この文で一番言いたいことは何なのか。〈人がいた〉と言う人の存在が言いたいのか、〈愛されることがあった〉という特別な愛情を受けたという出来事なのか。ぼくは後者に軍配を上げる。そこから逆算すると、〈が〉は主格と考えるしかない。〈が〉はそもそも主格が基本だから、文の構造として不自然さがない。補う語も〈人〉と〈語〉で、別々だから無理がない。〈が〉については以上。明日は〈時めく〉を検討しよう」
明日は月曜だが学校はないので、十時に集まる約束をして終会にした。
四回 時の流れとほころび
日が沈む少し前、JR秋葉原駅の中央改札口を南に降りた。突き当たりのワシントンホテルを右へ曲がる。通りは、五時を回ろうというのに人並みもまばら。マスク姿で街に繰り出すのは、日本人の専売特許のはずが、大きなマスクで顔を覆った外国人観光客が旅行鞄を引きずりながら三々五々、電飾街を闊歩する姿は異様に思えた。東北新幹線の高架下に入る手前の居酒屋で左に折れ、神田ふれあい橋という神田川にかかる小さな鉄橋の階段を上がり切ったところで人心地。十年来通い慣れた道だが、日没前に通ることは記憶にすらない。夕映えに赤く色づき、森厳さを深めた柳森神社の静寂ぶりが目に優しかった。
あれからもう八年。小雪のちらつく中、受験直前のヒロに柳森神社の泥人形、おたぬきさんをお守り代わりに渡したのは。「合格したら、花見に連れてってね」と言った、赤いマフラー姿のヒロを今もはっきりと思い出す。塾は橋を渡り、高架をくぐったすぐ先にある。
塾は閉鎖していたが、明かりを少し落とした講師室で、塾長が待っていた。
「自習室も閉鎖ですか」
「塾生から感染者でも出たらどうなる」
塾長の深刻な様子から、事の重大さが伝わってきた。
「LINEした通り、講習会は中止。ヒロと相談して、返金手続きを取っている」
ヒロから情報が入っていない前提の話だから、別れたことは耳に入っているのだろう。
「そうですか。それは痛いですね」
塾長は、ぼくの言葉を手で遮り、
「東京もいつロックアウト宣言が出るかわからない。入学シーズンだからって、生徒を集められないのはどこも一緒だ。今、この状況で、生徒に何が提供できるかだ。今年の英数の講習会は録画配信する予定だったのは知っているよな」
「テスト撮影の時、同席していましたから。先生方も張り切っておられたのに…」
「いや、入試速報でやれないかと思うが、どうだ?」
「それは、お二方に聞いていただかないと」
「二人はむろんオーケーさ。じゃなくて、全教科で速報だ」
ぼくは非常勤の身でありながら、関西の同じ大学出身ということもあって、何かと相談を受けた。ヒロとの同棲が塾長の耳に入ってからは、なおさら目をかけてもらった。ヒロが塾の経理を任されたのもその流れだった。
「確かに速報なら準備も何も不要だけど、でも、先生方が承諾するかどうか」
「普段の授業と録画では緊張度も違うけど、毎年やっていることだ。多少の不手際はライブ感があっていい。四月以降、授業を配信に切り替える。入試速報はその予行演習だ」
展開の速さに頭がついていかず、言葉が出なかった。
「学校は閉鎖、学童もできない。今この時、勉強したくてもできない状況を、どうにかしないとな。これは将来にわたる日本の損失だ。そうは思わないか」
「このままでは塾も予備校も閉鎖のままってこともありますね。となれば、ネット配信で、雇用が確保できるなら、先生方も助かる面はあるでしょう」
「録画を嫌がる先生は出てくるだろう。テストやテキスト作りに回ってもらうなり、そうだチューターがいいな。授業の補佐で、ネットやチャットで質問を受ける。講師は授業に専念してもらい、フォローアップに人材を割く。それなら塾の強みを活かせる」
実際に動き出せばいろいろと問題は噴出するに違いない。だが、ネットを介した基盤作りに、世の趨勢が向かうことは否定すべくもない。始めるなら今だろう。来年を待っていては、大資本に飲まれてしまう。そのためには資金の確保だが、感染症対策の名目で普段とは別枠融資を、信用金庫から取り付けていた。すでに塾は大きく舵を切っていた。
「入試速報は、YouTubeで流す。宣伝のためすべて無料だ。大手にはない細かなフォローが出来るかが勝負だが、勝算はある。後は時間との闘いだ」
「それは楽しみですね」そうは言ったものの、ここにはもう自分の居場所はない気がした。四月から授業を増やすことになっていたが、ヒロと別れた今その必要もない。
「そこで相談だ。経営を手伝ってくれ。高給は出せんが、非常勤よりは安定する。一人では回し切らんのだよ」
確かに、塾長一人でできる仕事量ではないが、思ってもみない話に返事が出なかった。
「わたしは授業の録画と編集にまわるから、君は副学長として、講師や生徒とのやりとりや、ホームページの更新、講師の紹介などを担当してほしい」
ヒロとあんな別れ方をしていなければ、こちらから願い出たいくらい有り難い話には違いない。だが、時間もヒロも戻らない。
「ヒロにも君に手伝ってもらいたいとの相談はした。やる気を出すなら適任じゃないかって。そろそろ、まじめに考えろ。彼女にも、会計士として理事に入ってもらう」
即答できる話ではないので、一週間待ってほしいと頼んだ。一週間は長いと言われたが、姪に源氏物語を教えないといけないので、今はそれに専念したいと伝えた。
「未曾有の災難に違いない。でも、数十年前に同じことが起きていたら、テレワークも何もない。壊滅的な打撃を受けただろう。今はネットがある。これを最大限に活用して、災害に強い、より良い社会に変えて行くのが現代人の使命だ」
塾長はいつになく熱かった。ぼくに何ができるだろうか、そんなことを考えながら、神保町に向かった。
靖国通りを西に向かい、駿河台下の交差点まで来ると、〈ABC-MART〉の赤い文字が立ちふさぐように現れる。神保町の古書街の始まりだ。今はそれを尻目に左折し、千代田通りを南下、神保町一の高層ビル、三井ビルディングの真向かいにあるG書店を目指した。薄暗いエントランスは、レンガ色の大理石が敷き詰められ、細い笹の葉のような幾何学模様が全面を覆う。ジュラ紀に栄えたネリネアの化石だ。左手に鉄の非常階段はあるが、ひどく錆びて利用する者はない。右手の奥にエレベーターが一台、七階で降りると、強風のためビルが揺れた。次元のはざまに落ちたような感覚にとらわれた。
拓本で目張りされた重厚なガラスの扉を何度かノックするが、店主はこちらを背に、パソコンに向かったまま気づかない。また小説でも書いているらしい。いつものことだから、ノックを続けていると、ようやくドアを開けてくれた。
「電話しなかったけど、よかった?」
「居れば開けるさ。留守に来られると出にくくなるだろ。電話してもらえると助かるんだ」
「そうか、客に電話をかけさせるのは、主人の心的ストレスを軽減するためか」
「相変わらずだなあ、きみは」
入り口横のソファーに腰を下ろすと、店主のNはようやく難しい顔をほころばせて、コーヒーを勧めてくれた。Nは高校の同級生だ。
「〈護月〉ってどうかな、小説のタイトルに。中島棕隠の扁額は見たことあるだろ」
「確か月蝕から月を護るとかって意味だったよな。精確には覚えてないけど」
「月蝕は災難の予兆だ。だから、祈祷や踊りとかをして月が闕けるのを防ぐ」
「それをどんな小説のタイトルに使う気だい」
「今の感染症社会にさ」
「現代小説なの? どういう風の吹き回し?」
「まあ茶化すな。ぼくなりの社会参加さ」
「それについてとやかく言う立場にないけど、今の感染症対策が、護月みたいなものだと言うのはシニカル過ぎないか?」
「逆だよ。月蝕に備えるためには、暦、数学、天文学という当時の知見が総動員されているはずだ。加えて、世の中の災いを招いた根本原因を突き詰める論理力や哲学も必要だ。陰陽五行思想だ。現代から見るとそれは科学でもなんでもない。でも、類推を働かせ、自然の奥にある見えない法則を読み取る。それは当時の最先端科学だったんだ」
「そうだな。それに天人感応説だな。天空と地上は感応し合うから、天空の秩序をただすことで地上の乱れをただす。東洋思想の根幹だ」
「さすがだね。君もよく天を仰ぐからな。ハハハハハ」
「どういうことだ?」
「君は今度の小説の主役の一人だってこと」
「はあ? じゃあ、登場人物にタイトルの相談をしたわけか。なかなか奇天烈だね。是非とも読ませてもらわなくちゃ」
「ご勘弁願うよ。登場人物だから、話は知っているはずだし、小説から飛び出して、読むこともできないだろ?」
二人は笑い合った。
「今、何より大切なのは、想像することだ。普段の行動のままだと、二週間後にこの世にいられる保証は誰にもない。だから、かからない、うつさないために何ができるか、類推を働かせることが重要だ。それが次の世の秩序を生み、道徳を生む」
Nはいつになく熱い。
「あたうべくは、科学的にな」と、ぼくは付け加えた。
Nもぼくと同じ現実逃避組だと思っていたから、なかなか考えさせられた。ぼくはインターバルを取るように、山積みされているレファレンス棚から、旧版の『例解古語辞典』を取り上げた。Nが目ざとく質問した。
「また家庭教師でも始めるのか」
東京で塾講師を始めた頃、Nも上京してG書店を立ち上げた。旧交を温めがてら、塾には内緒でヒロの家庭教師を始める際に相談をしたのがNだった。最初のデート、千鳥ヶ淵の桜を見た帰りにも、G書店に立ち寄った。
「古文教えてと、せがまれたのさ」
「誰に、〈若紫〉か」
ぼくは少し顔を赤らめながらうなずいた。『若紫』は、後に妻となる紫の上を光源氏が見初める物語で、Nはミサキを指す隠語として使った。本名ナカムラミサキからの命名だ。彼に言わせれば、ヒロに煮え切らない態度を取るのは、若紫の存在ゆえだと。〈紫シンドローム〉と冷やかした。ぼくは否定も肯定もしなかった。
「ヒロは、OKしたの」
別れたとは言えなかったが、首を少しだけ横に振った。ぼくは窓辺に寄った。千代田通りと公園をはさんで、オフィスビルが林立する。
「で、〈若紫〉と何を読むの」
「源氏の冒頭」
Nもさすがに言葉を失った。ぼくが十年間苦しんだことをよく知っている。
「いい機会じゃないか。高校生にもわかるように説明できたら、言うことない」
「ぼくもそう思って引き受けた。できるだけのことはするつもりだ」
人に教えるにも類推が大切だ。その説明で相手に伝わるのか想像できないといけない。でも一体ぼくは何を護るのか。源氏ではない。自分でもない。ヒロがいればヒロだろう。でも、今護るべきは…。ぼくは塾長の話を真剣に考えてみることにした。だが、その前に、ミサキの宿題を片付けよう。
五回 いかなる〈時〉の到来か
原文八:きのうのおさらい
いとやむごとなき際にはあらぬ(人)が、すぐれて時めきたまふ(こと)、ありけり
「今日のテーマは、〈すぐれて時めきたまふ〉だね。一般に、文のストレス、つまり意味の核は、文末の述語が担う。この文では〈ありけり〉が文末の述語だが、これは存在を表す形式的な動詞に過ぎないから、意味の中心は〈時めく〉にある。だから、この語はとても重要だ。最初に意味だけど、〈時めく〉の主体は何だった?」
「書いてはないけど、桐壺更衣であることが後からわかる」とミサキ。
「よく覚えているね」
「意地悪されたからよ」と、大きな口で笑う。
「〈すぐれて〉は動詞の〈すぐる〉から派生した副詞で、人にまさる、抜きん出る、秀でるって意味だ。副詞だから用言、この場合〈時めきたまふ〉にかかる。ここまでは問題がないね。では、〈時めきたまふ〉の訳から検討しよう。どうなっている?」
「〈寵愛を受けていらっしゃる〉ってなっているわ」と、ミサキ。
「辞書もだいたいそんな感じだが、〈時めく〉は自動詞だろ? どうして受身の訳になるのか。それに、男性に用いる場合と女性に用いる場合で、意味構造が違う点も疑問だ」
「意味構造って?」とミサキ。
「じゃあ、辞書から訳例を転記するよ。〈時〉と〈めく〉の意味もまとめておく」
○対男性:権力者に取り立てられて、栄える・はぶりがよくなる
○対女性:帝などから恩寵をうける
○時:好時節、人生の盛り、好機など時に関する表現
○めく:目や耳を通して、そういう状態に近づく。それらしく感じられること
例:春めく・色めく・今めく・ことさらめく・ざわめく…良し悪し両方に用いる
「ドキドキするという今の時めくと関連がないのかな?」と、ヒロが聞く。
「〈心時めきす〉という古語があって、これが現代の時めくに当たる。心時めきすは、大事な時が来て、心が躍るって意味で関連はあるけど、〈時めく〉は心の状態ではない」
「構造が違うって言うのは、男性は二段階、女性は一段階のこと?」と、ミサキ。
「男女の使用例を見てみよう。〈権力者〉と〈帝〉、〈取り立てられる〉と〈恩寵を受ける〉が対応している。男性の場合は政治の世界で、女性の場合は後宮の世界で使用される。ただし、女性の場合には、ミサキの言う二段階目がない」
「女性では、〈時〉に対応する意味がない。だから一段階なのか」と、ヒロ。
「〈時めく〉は、待ち望んでいた〈時〉が到来したという意味だけど、その部分の訳がない」
「時がないんじゃ、〈時めく〉にならないじゃないの」と、ミサキが不満げに言う。
「〈時めく〉の最も有名な例は、この源氏の冒頭だ。どの辞書もこの文を引用する。ところが、桐壺更衣は、嫉妬されたり、意地悪されたりはするけど、出世や栄達とは無縁のまま人生を終える。つまり、男性の栄えるの意味を、桐壺に当てはめることができない。だから省いた、まあ推測だけどね。結果として、〈時〉の意味が消え、受身の意味が残った。実際、死後に位は上がるものの、生きている間は苦労が絶えない。その原因こそ、身分不相応な帝の寵愛だ。社会的ランクは確かに変化しない。でも、帝の特別な寵愛を受けながら、全くランクが上がらないなんてはずがない。それを考えたい。こういう時に役立つのはそもそも論だ。女御や更衣たちは、どうして帝に仕えているのかな?」
「それは、子を産むためよ」と、ミサキ。
「何のために?」と、畳みかける。
「天皇や皇太子につけたいからよ。だって、そうなると家が繁栄するもの」
「そうだね。桐壺更衣は、線が細く、周囲に翻弄されるだけのイメージだけど、帝の子供を産むために、自ら進んで後宮に入ったことが母の説明でわかる。桐壺の身分では、待っていても希望はかなわない。帝の気を引き留める努力をしたはずだ。身分の低い桐壺ができる努力って何だと思う?」
「女の魅力って言いたいけど、そんな受身じゃ、競争相手に勝てないわね」
「女の魅力には違いないけど、ここは後宮だろ。後宮を考えるポイントはただ一つ、性の場だってこと。だから、セックスアピールこそが、帝を引きつける最大の武器だ」
女御の武器は出自、更衣の武器は床上手
原文九と訳 女御にはさせられない下働き
初めより、おしなべての上宮仕へしたまふべき際にはあらざりき
初めから、帝の側仕えをしなければならない身分ではございませんでした
「〈上宮仕へ〉は、帝付き下位の女官で身の回りの世話をする。そこで具体的に示されている例が二つ。
さるべき御遊びの折々、何事にもゆゑある事のふしぶしには、まづ参う上らせたまふ
立派な管絃の会や、格式ある行事には、どこにも真っ先にこの方をお側にお召しになる
「〈参う上らせ〉は、桐壺更衣が自分の局から帝の側に参上するように呼びつけたこと。管絃の会や行事に参加させるだけなら、上宮仕へにならない。その折りの帝の身の回りの世話などをさせたのだろう。後宮の女性がやる仕事ではない」
ある時には大殿籠もり過ぐして やがてさぶらはせたまひなど
ある時には、共寝したまま起きそびれて、そのまま側仕えをおさせになるなど
「寝過ごして、そのまま桐壺を局に返さなかったという意味は、政庁にも顔を出さず、朝からセックスに励んだと言うことだ。天子が政務を行う場所を朝廷というのは、帝は、朝、働くからだ。日の出から陽の気が満ちる正午までが、男社会を束ねるのに有効な時間で、百官が帝の裁可を待っている。なのに、桐壺といちゃつくとは何事だって話。ただし、現代人と性に関する認識が違う。今日、後宮制度など認められていない。その一点でも推して知るべしだが、平安時代に書かれた『医心房』って医学書があって、『素女経』などの中国の古典に基づいた著作だけど、セックスは回数が多いほど寿命が伸びるという趣旨のことが記されている。男は陽の気が、女は陰の気が、それぞれ多くバランスを欠く。健康で長生きするには、セックスにより足りない気を補わねばならない。その際、高まった気を失わないように射精しないことが重要で、回数を重ねて、気を整えた。性に対する重要度が今日とは格段に違う。身分で劣る桐壺が帝を独占できたのは、性による結びつきだ。愛情もそれなしにはあり得ない」
おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせたまふあまりに…中略…おのづから軽き方にも見えしを
帝の愛情はこれ以上にないほどで、女御にも見まがう様子でしたのに、帝がむやみと側にお留になるばかりに…おのずと品下る方と見られたものです
「中略部分には、今の具体例などが入る」
「〈上衆めかしけれど〉って、どういうこと」と、ヒロが質問する。
「〈上衆めかし〉は、いかにも貴人のように見えたと訳される。ポイントは、実際の位よりも上に見えたってことだ」
「それが〈時めく〉?」と、ヒロ。
原文A:いとやむごとなき際にはあらぬが(=女御ではないが)、すぐれて時めきたまふ
原文B:おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれ(ど)(女御のように見えたけど)
「二つのフレーズは同じことを言っている。結局、桐壺は女御ではないけど、女御並の愛情を帝から受けたおかげで、まるで女御のように高貴に見えた」
「説明はわかるけど、訳してよ」と、ミサキ。
「あえて訳せと言うなら、帝の寵愛を受けて、今を時めく存在となった、くらいかな。使える言葉はそのまま活かす。好みの問題だけどね。でもそれでは、時めきの中身はわからない。ぼくがそこに注をつけるとしたら、こんな具合だ」
――桐壺更衣が主体的にふるまったのは、冒頭の〈時めく〉と、死の直前の歌しかない。この歌に対する帝の返歌は死後に行われるから、宙に浮きっぱなしの状態だ。だから、〈時めく〉を帝に〈寵愛された〉とだけで済ますなら、桐壺更衣は生涯、受身だけの人生で終わる。死ぬ時は一緒と帝と誓い合った女性が、喜びで輝かないはずがない。桐壺の亡き後、瓜二つの容貌である藤壺が入内する。桐壺と藤壺は血の上でもつながりがある。光が生涯追い求める女性を紫のゆかりといい、藤壺、紫の上、明石の御君等が挙げられるが、それは母の血に他ならない。藤壺は〈輝く日の宮〉と呼ばれ、光源氏の〈光〉と相称されるが、それは母から受けた美質だ。それこそが〈時めく〉なのだ。帝はそのとりことなり、それを受け継いだ光源氏を、特別扱いせざるを得ないのだ
ぼくは、ヒロのことを思い出していた。ぼくは彼女を時めかすことができただろうか。そんなことを思いながら、ぼんやりと今引いた原文を見やっていた。
「そうか」と、ぼくは思わず立ち上がった。
「またトイレから飛び出すの」と、ミサキがひやかす。ヒロはよくわからない様子。
「ちょっと待って」と制し、今思いついたことを整理した。
いとやむごとなき際
○元の訳:最上級のランク
○改訳:帝が最上級に尊重すべきランク
○内実:性交渉として選ぶランク
「〈やむごとなし〉には、この上ないという意味と、この上なく大切だという二つの意味がある。〈際〉と関係深いのは前者だから、意味もそう取っていたけど、内実を考えたら、後者しかない。ここは後宮だ。尊重するとはどうすることか? それは性の対象として大切にすることに他ならない。具体的には、独り寝の苦しみを味わうことがないように性の相手に選ぶこと。それが〈いとやむごとなき際〉の後宮女性に対する帝の礼儀だ。ところが、女御ではない桐壺更衣が、女御が受けるような寵愛を受けた。つまり夜ごとの性の相手に選ばれた」
「つまり、実質、後宮トップの座を射止めたわけね」と、ミサキが引き取った。
「後宮の女性として帝を独占することは何よりの名誉のはずだ。帝を独占できれば、息子の競争相手が増える心配はない。つまり、戦略としても理想的だ。いろいろ言ったけど、この文は桐壺更衣の客観的描写ではなく、帝がいかに桐壺を愛したかを述べたものだ。だから、上から下まで桐壺と帝は切り離せない。〈御時〉が帝で、〈時〉が桐壺、まあそれは冗談だけど。〈時めく〉は、しっとりと濡れ輝く、帝の性ホルモンを刺激して止まない美だ。それはそうと、この帝がいかに光源氏を特別扱いしたかを見ておこう」
一の皇子は…中略…おほかたのやむごとなき御思ひにて この君をば わたくし物に思ほしかしづきたまふこと限りなし
第一皇子に対しては…中略…型どおり尊重しようと帝はお思いでしたが、この君に対しては、私物にお思いで大切にお育てになる様子は限りがございませんでした。
「〈わたくし物〉って」と、ミサキ。
「生まれて間もない光に注いだ帝の愛情だね。具体的には述べられていないので推測するしかないが、公との対比から考えると、帝の思い通りにできる存在、人から干渉を受けにくい存在、自分だけの存在、そんなところかな」
「公には規則があり限度があるけど、プライベートは帝の領分で、人が口出しできない。だから限りなく愛情を注ぐことができたって感じかな」と、ヒロ。
「女御は公的存在で、更衣は私的ニュアンスが強いってことだったわね」と、ミサキ。
今日、ぼくが一番伝えたかったこと
「公よりも私を優先する。これが源氏物語の基調の一つだ。桐壺帝は更衣のために、政治を投げ出し、国を傾ける。息子の光源氏は、母の後妻に入った藤壺と関係を結び、子をもうける。その子が成長して帝になるが、実の父が光源氏と知って、皇位を光に譲ろうとする。これらみな、公よりも私を優先している」
「なるほど、血の流れとなって代々伝わっていくのね」
「今日はなかなか面白かったわ」と、ミサキが振り返った。「でも、しっくり来ないのよ。帝が政治を投げ出し、女色に溺れ、私的感情に走るなんて天皇批判を、紫式部はどうして書けたのか、なぜ咎めを受けなかったのか、それがわからない」
「いい質問だ。源氏物語が拠って立つ時空間、その答えこそ、ミサキの好きな、ぼくのユウレイカだ」
「幽霊か? ああ、我発見せりのことね」と、ヒロ。
「なんで私が好きなのよ。単なる露出狂のくせに」
「人聞き悪いなあ」
「風呂から飛び出したの?」と、ヒロがミサキに聞く。
「トイレよ」と、ミサキ。
「マジっすか、すげえ」と、大げさに驚く。
「パンツははいていたろ」と、反論する。
「そうだったかしらね、ふふふ」と、ミサキは含み笑い。
「気にせん気にせん」とヒロが、ちょっかいを出す。
「頼むから、事実を曲げないでくれよ。それはともかく、今のミサキの疑問は〈いづれの御時にか〉を読み解くことで解決できると思う」
「ほんとに? そんな十字足らずの語数でそれだけの情報、詰め込めるかしら」
「眉につばをつけましょうか」と、ヒロがふざける。
「言うねえ。まあ、明日を楽しみにしてよ」と、お開きにした。
終回 物語の現在性、モノをカタルとは
原文十 最初にして最大の難所
いづれの御時にか
「じゃあ今日は、いよいよ〈いづれの御時にか〉だね。まずは、どんな風に訳されているか、見ていこう」
「どの帝の御代のことであったか、いくつか調べたけど、だいたいそんな感じだわ」
「このフレーズを理解するには、次のようなステップを踏む必要がある」
ステップ一:絶対時間と天皇名
ステップ二:天皇名のルール
ステップ三:源氏物語における天皇名
ステップ四:結論づけられる物語時間
ステップ五:この文の解釈
「これまでの文の解釈とは全然違う感じね」と、ミサキ。
「源氏物語の時間設定がどうなっているかを先に考えた上で、このフレーズの解釈を決めるという手順を踏む。遠回りをする理由は、それをしないと、〈どの帝の御代であったか〉という訳の問題点が浮かび上がらないからだ」
「なんかゾクゾクする」と、ヒロ。
「時間の表現には、相対時間と絶対時間がある。呼び名は難しいけど、普段使っている表現だ。今を基準に何年前というのが、相対時間。今は百年前になったり、百年後になったりする。今がズレることで、指し示す時間も変化する。だから相対時間だ」
「じゃあ、絶対時間は、西暦とか、元号とかね」
「その通り。何年と特定して動かないのが絶対時間だ。ただし、源氏物語には西暦も元号も出てこない。残る絶対時間の表し方は天皇名だけだ。天皇の在位何年目という形で絶対年を示す。実は、元号も天皇在位の下位区分だから、西暦以前に絶対時間を表すのは天皇名しかない。まずこの点を押えたい」
「でも、どうして天皇と時間が結びつくのだろう? 西暦もキリストの生誕と関連するけど、似たようなものかな」と、ヒロ。
「時間は統一支配のためにある。個々人ばらばらの時間を使うと支配が難しい。統一した暦があるから、計画を立て、巨大事業が完成する。この国は、中国の支配を受けていたので、統治権を認めてもらう代わりに、中国皇帝が決めた中国暦を使用した。これを冊封体制というけど、中国から独立した時に、天皇が時間の支配者となった。西洋の場合は、おそらく教会が時間を決めた。だからキリストの生誕を基準にしたのじゃないかな」
時間の大原則
絶対年=天皇名+在位年(時間は天皇が支配する)
「今、天皇名が年代を表すと言ったけど、天皇の名付けには厳格なルールがある。現在在位にある天皇には、固有名をつけない。上とか今上帝などと普通名詞で呼ぶ。名前をつけるのは退位後のこと。院になれば院号、死後には諡号が贈られる。つまり、現在は今上帝在位何年と表し、過去は諡号と在位年で表す。日本史でなじみの天皇名はみな諡号だ。だから生前そんな風に呼ばれていたわけではない」
時間の原則一
過去の年号=諡号(固有名詞)+在位年
時間の原則二
現在の年号=今上帝(固有名のない普通名詞)+在位年
「ところで、天皇名は、なぜ絶対年を表せるのだろうか。それは天皇名に重複がないからだ。たとえば中村さんなら、どの中村さんという質問が成り立つ。一方、桓武天皇は一人しかいない。どの桓武天皇という質問は成り立たない。考えてみると、特定するものは名前に限らない。桓武天皇の名前を忘れても、平安遷都した天皇だとわかれば、天皇を特定したことになる。平安遷都をした天皇は一人しかいないからだ」
天皇の特定
固有名、または特定できる事績・行為など
「でも、どうして今上帝には固有名をつけないのかしら」と、ミサキ。
「同じ年代に天皇は二人いない。だから、その時々の年代で、今の天皇と言えば、名前はなくても、天皇を特定できる。名前で呼び分ける必要がない。もし退位されたり、亡くなったりすると、退位した天皇や亡くなった天皇はたくさんいる。だから固有名をつける必要が生じる。ただし、今の理屈だと、必要がなくても便利だから、今上帝に名前をつけようという議論が成り立ってしまう。しかし、日本の長い歴史の中で、それは行われて来なかった。なぜか。言霊思想があるからだ。名を呼ぶことはその人の正体を知り、掌握することになる。だから、在位中は特定の名を持たない。苗字さえない。名付けてはいけない」
「続いて、源氏物語の中で、天皇名がどうなっているかだが、最初に大事な注意がある。これまで便宜上、桐壺帝・桐壺院などと言って来たが、全部うそだ」
「うそってどういうことよ?」と、ミサキはおそろしい顔になる。
「そんな呼び名は、源氏物語のどこにも出て来ない」
「でも、調べていた時、見た気がするわ、どこだか覚えていないけど」
「説明や注釈を作る際に、特定する名前がないと不便だろ。だから、名前をつけた。光源氏の母には、〈桐壺更衣〉という呼称がある。呼称とは源氏物語のテキストとして実際に使用例のある呼び名のこと。しかし、桐壺帝という呼称はない。桐壺更衣を愛した帝だから、桐壺帝と呼ぶことにしただけ。これを慣用の呼称という。昔から習慣として用いられる呼び名のことだ。源氏物語の登場人物は、位が上がったり、役職が変わったりして、同じ人物でもいろいろと呼称が変わる。誰がどこでどう呼ばれているか、しらみ潰しに調べられている。光源氏の父の呼称には、桐壺帝も桐壺院もないし、亡くなった後に諡号も贈られない。徹底的に固有名が避けられている。では他の天皇はどうか。朱雀や冷泉も、朱雀帝や冷泉帝の呼称はないし、諡号もない。退位後は朱雀院・冷泉院と呼ばれるが、これは建物名であって院号ではない。だから普通名詞だ。今上帝はもちろん名前がない」
源氏物語では、在位中も在位後も、帝は固有名を持たない
「親切な注釈者なら、この呼称は慣用であって、本文にはない呼び名だと注記する」
「名前がないから注釈者がつけたのはわかったけど、不便だからそうするなら、作者こそ不便なのに、どうして紫式部は、名前をつけなかったの?」と、ミサキ。
「それを考えてもらいたい。天皇に名前をつけるのは、退位後や死後だった」
「ということは…、そうか、在位にある天皇だから、名をつけない。つまり過去じゃなく、今を描いているわけね」とミサキは両手をあげた。
「Good job!だけど、それだけでは院号もつけない理由にならない。でも、それは後回し。ここまでわかったことで、〈いづれの御時にか〉の訳文を検討し直してみよう」
原文十一
いづれの御時にか
どの帝の御代のことであったか
「この文を〈語り手〉が語り始めた時のことを想像してほしい。話題は桐壺更衣であり、時代はそれを愛した帝が在位していた時代だ。帝には名前こそないが、この天皇だけが行った事績、つまり桐壺更衣を溺愛したことで、特定されている」
「物語に則して言えば、そうなるわ」と、ミサキ。
「では〈どの帝の御代のことであったか〉という質問は変だよね。今上帝に名前はない。この帝のみが行った事績で特定もされている。だから」
「どの天皇という疑問文は成立しない」と、ヒロが引き取った。
「もしこの問に、桐壺帝と答えたとしたら、つまり〈桐壺帝の御代に〉で物語を始めたらどうなるだろう」
「桐壺帝と呼べば、もう帝は死んだ人になる。名付けないことで、まさに今天皇が、更衣を愛している姿を描くことができるのね」とミサキ。
「どの帝の御代か、それに答えようとすると帝は死んでしまう。名前と今上帝を同時に取り込むとパラドックスが生じてしまう。それを解こうとして苦しんでいたわけ」
「それが、トイレイカね」と、ミサキとヒロが声を揃える。
「それギャグ? 二人で考えて来たの? 暇だねえ」
「ガクよ、ガク。アハハハ。で、解けたのね」と、ミサキ。
「解けない」
「えっ、解けないのにトイレイカしたわけ」と、ヒロも図に乗る。
「まあまあ。解けないけれど、答えは出た」
「どういうこと? それもパラドックス?」と、ミサキ。
「単純な論法だ。〈御時〉とは時代のこと。時代とは天皇の名。しかし、現在だから天皇に名はない。つまり、この物語は現在時間で推移すると考える。名前はないのではなくて、名付けない」
「よくわからないけど、コロンブスの卵みたいなもの?」と、ミサキ。
「〈か〉を疑問とするからパラドックスが生まれる。反語と考えれば問題は生じない」
「まるで、コロンブスの卵だわ。何を言っているのか、さっぱりわからない」
「コロンブスの卵をどう理解したら、そんな言い方ができるのか、さっぱりわからないけど、古文の授業風に反語で訳すとこうなる。〈いずれの帝の御代と言うことができましょうか、いやできません〉つまり、冒頭のフレーズは、名をつけない宣言だ」
「帝に名をつけないことが、イコール時代設定を現在におくってこと? ちょっとしっくり来ないけど」と、ヒロ。
今日、ぼくが一番伝えたかったこと
「現在に呼び出しているという方がいいな。〈モノ〉とは、触れる事の出来ない異界。それは過去であったり、空想であったり、それを今に呼び出すのが〈カタリ〉だ。語られた物語を読みながら、頭の中で物語を再構築する。語られている物語自体は、現在には属していないが、本を開く度に、語りは再現される。だから語ることで、物語は今に呼び出される。それを今、頭の中で描き直す。だから、登場人物は生き生きと感じられる」
その時、電話が鳴った。画面にヒロの文字。ミサキが。〈あっ〉と声を発して固まった。何か隠していることは間違いない。ぼくは動揺を静めて電話に出た。
「たいへん。塾長が過労で倒れた」
電話が切れた。かけ直すが通じない。塾からだ。塾は東北新幹線の高架が近いので、新幹線が通ると、電波が途切れることがある。
「どうしたの」と、ミサキが心配した。
「塾長が倒れた。悪いが行かなきゃ」
こんな時、交通機関はラチが明かない。近くのシェアサイクル・ポートへ走った。大慌てで自転車をこぎ、塾に駆けつけた。
立ち現れるモノ、立ち去るモノ
やはり、ヒロは塾にいた。
「過労だけだから二、三日で出られるそうだけど、こういう状況だから面会もできないし、これで熱でも出たら、隔離された上で検査になるそうよ。そうなったら、連絡も難しくなる。最悪の場合も考え、今、指揮系統を一任しておきたいって。ねえ、どうするの?」
このままでは入試速報もぽしゃる。新学期の募集もできずに、塾は立ちゆかなくなる。だからと言って、ぼくに何ができるだろうか。黙っているぼくにヒロは業を煮やし、
「どうするの。このままだと塾、なくなっちゃう。それでいいの」と、言って泣き出した。
「塾長が戻るまで踏ん張ろう。やるしかない。だから、私情を捨てて手伝ってくれ」
塾長が過労で倒れたことと、ぼくが塾長代理を務める旨をLINEで回した。その上で、入試速報に変更はなく、承諾確認を改めて行った。今まで録画をしぶっていた講師からも、この状況で断るわけにはいかないと、積極的な協力を得ることができた。塾への恩返しというワードがLINEにあふれた。みなそれぞれに塾への、塾長への思いがあるのだろう。信用金庫からも融資が下り、資金は潤沢だった。塾は数年前に株式組織に変更している。塾長の許可があり、印鑑類はヒロの管理下にある。資金を使うことに問題はなかった。
準備は着々と進んだが、入試日直前になって、主要科目の講師たちが大手予備校に囲い込まれてしまった。さすがにこれは参ったが、それぞれ生き残りに必死なのだから致し方ない。教科主任と話し合った上、思い切って速報をやめることにした。代わりに、期間を二週間ずらし、しっかりと授業準備を整えた上で、通常の授業と関連づけた入試解説に切り替えた。入試速報は力の見せ所ではあるが、合否の定まらぬ受験生は上の空で、真剣に聞く耳を持たない。浪人生をターゲットに絞ることで、授業に身が入り、結果として聴講者が増えることが期待できた。ドタキャンをして、責任を感じている講師の多くも、時期をずらすことで、呼び戻すことができた。大手に囲い込まれるだけあって、優秀な先生方だから、縁が切れてしまうことは塾として痛かった。
私学入試においても国公立の入試でも、時期をずらしたことは功を奏した。浪人する場所を決めている生徒に募集をかけても意味はない。進路を決めかねている生徒にこそ、アピールしたい。すでに多くの塾が募集を終わらせていたが、ネット配信の強みはいつでも入塾可能な点にある。卒業式シーズンに入る頃から、じわじわと生徒が集まり出した。
塾長からは、数日どころか、ひと月にもなろうというのに、連絡が途絶えたままだった。ヒロを通じてしばらくは指示があったが、それもなくなった。考えれば不安になるので、忙しさにかまけて考えないようにした。四月に入り、東京都では、公立高校が五月の連休明けまで休みを延長することを決めた。その受け皿になれるよう、五月まで無料配信を行うことにした。桜の季節が終わる頃、LINE電話が入った。塾長からだ。
「よくやってくれた。毎日ヒロから連絡はもらっていた。なぜ顔出さないって? そこはもう、おまえが塾長だ。わたしが出る幕はない。実は、こっちも新しい塾の立ち上げに手一杯でな。今度は、小中対象の補習塾だ。今は学童も機能しないだろ。地方地方の塾と提携して、配信授業ときめ細かいフォローアップの両輪でまわす。来年には小中でもタブレットが一斉に配られるだろう。今から、そのコンテンツを準備して、学校や教科書会社に売り込みをかける。学習指導要領も、これからは映像に変わるだろうからな。まあ、今度飲みに行こう。正式な塾長任命はその時だ」
補講 役者は退場、風が遠くの鐘の音を運ぶ
四月六日、母の命日、非常事態宣言が明日にも出る見通しだと言う。ゴールデンウィークが終わるまでの授業は録画済みのため、しばらく先生方には休んでもらうことにした。久しぶりにミサキとヒロことタカオが遊びに来た。本家のヒロが招いた。ヒロは塾長が倒れて以来、改めて関係を修復したわけではないが、戻ってくれていた。皆が揃ったのだから授業をしろと、ミサキがせっついた。質問形式だと時間がかかるので、今日は講義という形にしてもらう。
原文十二 訳 時の原則
いづれの御時にか
どの帝の御代のことであったか
原則一:過去の時代は天皇名で表す
原則二:現在を表す天皇名はない
「まずは、天皇と名前の関係について考えたい。〈いづれの御時にか〉の扉を開けるカギがそこにあるからだ。
源氏物語は、七十数年にわたる長編物語だ。その間に四代の天皇が登場する。桐壺・朱雀・冷泉・今上の順だ。今上とは在位にある帝を指す普通名詞。日本では、在位中の天皇に固有名をつけないルールがある。令和の今日でもそうだし、この物語の中でも厳密に守られている。桐壺・朱雀・冷泉と言ったのは、便宜的につけた慣用名だ。帝は、〈上〉〈国王〉など、普通名詞で呼ばれる。桐壺・朱雀・冷泉などの固有名は本文に出てこない。
では、退位した後はどうなるのか。退位後には院号が、死後には諡号を贈られるのが古来からのルール。日本史で見る天皇名はみな諡号だ。ところが、源氏物語では、諡号が出て来ない。死後も故院や父帝など普通名詞で呼ばれ続ける。
では、院号はどうか。光の父帝の場合、桐壺院の呼称はない。院などやはり普通名詞で呼ばれる。それに対して、朱雀院や冷泉院の呼称は頻出する。だが、これは固有名詞ではない。院号は、元来、天皇が退位後に住む建物の呼び名であった。その建物は、代々受け継がれ、複数の天皇が退位後に使用するものだった。歴史上、複数の上皇に使用されたことがはっきりしている建物名こそ朱雀院と冷泉院だ。従って、朱雀院と言う時、その建物を使用した複数の天皇を指す場合がある。これは普通名詞だからどの天皇か特定できない。これとは別に固有名詞の場合がある。この建物を最後に使用したため、この上皇の院号にもなった、第六一代天皇朱雀帝の退位後の名前だ。物語の朱雀院は歴史上の朱雀院ではありえない。兄弟に光源氏がいたりしないからね。従って、源氏物語の朱雀院は、朱雀院という建物を使用した院の一人でしかない。事情は冷泉院も同じである。
長々と話してきたのは、源氏物語の中では、在位中はもちろん、退位後も死後も、帝に固有名を与えられていないことを確認したかったからだ。これは実時間の歴史とは著しい違いだ。なぜ作者は、帝に固有名をつけなかったのか。一つには、物語を現在進行として語るという手法の問題がある。物語の冒頭をゼロ時間として、そこから刻々と時間が進んでゆくという物語時間を作者は選んだのだ。仮に歴史書のような固有名を帝につけたなら、それは諡号となってしまう。それでは生き生きとした物語は作れない。だから、固有名を出さない選択をした。
しかし、この説明では、トリックを使ってまで普通名詞に徹した理由の説明にならない。前に言霊信仰について触れたことがある。名前はその人の存在全体と密接に関わる。名前を知ることはその人を把握することだ。名前を知ると知らないとでは、呪いの力も違ってくる。そういう支配を避けるために、帝はそもそも名前を持たないのだった。名前があることはそれだけ重いのだ。一方、源氏物語が語る世界は、帝が女色に溺れたり、妻が息子に犯されたりと、およそフィクションでなければ描くことができない世界だ。つまり、フィクションの自由度を最大限に活かすためには、帝にも院にも存在の重みを増してしまう固有名がない方が都合がいい。時間とは帝の名であった。すると、帝に名がないことは時間までもが自由になる。
即ち、時空間を極力、実社会から遠ざけることに意を注いだのだ。なぜか。それは作者が物語ろうとした呪力があまりに強く、作者をも恐れさせたからだと思う。光源氏の父は亡くなった後、実子である今上帝の夢枕に立ち、にらみつける。これが眼病を引き起こし、帝は帝位を降りる決断をする。つまり、亡き天皇が今上を呪力で帝位から外してしまう。これは皇統を絶やす願いを立てて亡くなった崇徳上皇が、史上最も強い呪いとされ、事実明治天皇は、即位に先立ち、隠岐から京都に御霊を呼び戻し、白峯神社を建てているほどだが、実際に実子の帝位を取り上げた点では、それに勝るとも言える呪力だ。怨霊封じのために創出したのが、帝に名を与えない時空間なのだ。
その当否はさておき、〈いづれの御時にか〉の〈か〉は疑問でなく反語である。下に〈あるべき〉などが省略された挿入句で、〈いづれの御代でもないが〉〈いづれの御代とも申し上げられませんが〉などの意味となる」
その時、玄関にチャイムが鳴った。ヒロが応対に出た。「ミサキ、例の荷物、届いたわよ」
「限りなく現実との接点をなくしたフィクションだから、天皇批判や呪いが作れたって話ね。あっ、この荷物は気にせんで。ほら最後、がんばれ!」と、ミサキが発破をかける。
●コメント:いづれの御時にか〈〈語り手 聞き手〉…現在〉
●桐壺物語:女御更衣あまた… 〈〈語り手 〈物語〉…物語現在 聞き手〉…現在〉
「ここで冒頭に戻って、物語がどのように読み手の前に立ち現れてくるかを見ていこう。語り手が〈いづれの御時にか〉と語り始めた時、聞き手との間に現在時間を共有する。私たち読者も、読むことで聞き手の仲間に入り、現在時間を共有できるのだ。従って、〈現在〉という時間は、物語と実時間が共有し合える特殊な時間だと言える。
続いて、〈女御更衣あまた…〉と語り出す時のことを考えたい。便宜上この物語に桐壺物語と名をづけよう。先ほどまでは、語り手も、聞き手も、読み手も、まだ桐壺物語の外にいた。外から、語り手がコメントしたのが〈いづれの御時にか〉であった。
さて、〈女御更衣あまた…〉と語り始めた時、語り手はどこにいるのだろうか。桐壺物語の内か外か。それを考えるには、源氏物語の〈語り〉の設定を知る必要がある。
源氏物語はいろいろな場面を描くが、場面場面に女房が控えていて、後日、その実体験を〈語り手〉に語る。その実話を元に〈語り手〉が物語を語るという設定になっている。ここでも、帝の名を隠したと同じように、物語の世界が実体化しないように綿密に工夫されている。〈語り手〉には直接経験がない。その意味では物語から疎外されている。一方で、登場人物と直に接している女房と直接話を聞いている。これは物語内の人にしかできない特権だ。語り手は唯一、物語の中の人とも外の人とも話ができるのだ。これを視覚化するなら、物語の世界と聞き手の世界との間を隔てる扉が語り手なのだ。
扉は閉まっている。聞き手は語り手の話を聞くことしかできない。読み手もそれは同じだ。書かれていることを、頭の中で再構築するだけで、直接扉の向こうの世界に触れることは許されないのだ。
〈もの〉とは、人の力では動かせない、変えられない、近づけない領域。即ち、異界の存在だ。幽霊を〈もの〉とか〈もののけ〉とか言うのもそのためだ。時間を隔てた過去も同じ。今それを変えることはできない。過ぎ去ったもの、あるいは非現実のものを、今ここに呼び出すのが〈語り〉だ。言葉以前の〈もの〉の世界を、語り手というフィルターを通して、言葉に変換する。物語世界はあくまでフィクションだ。物語世界が本当にあると信じるのもよい。その場その場で話がでっち上げられると考えてもよい。扉は閉まっている。だから、類推を働かせる以上のことはできない。〈もの〉と〈聞き手〉をつなぐのが〈語り〉である。同様に、〈もの〉と読み手をつなぐのが〈書物〉だ。読み手がいなければ、書物は眠ったままだ。だから、みなさん、書物を読もうじゃないか」
ぼくは語り終わった。しばらくは興奮が冷めなかった。
「じゃあ、兄さん開けてよ」
「えっ何で、ミサキの荷物を開けなきゃならないんだ」
「開ければわかるから」
講義のお礼でもくれるのかと思った。それにしてはデカい。
「あれ、三つ入っている」
「ああ、それはわたしので、そっちは姉さん。で、これがショウゴ」
やっぱりヒロでもタカオでもないのか。中には、きれいな包装紙につつまれた箱が三つ。それぞれの品を受け取ると、立ち上がり、
「ありがとうございました」と、深々と礼をした。
ぼくは全く何のことかわからない。
「あら、鳩が豆鉄砲でも食っているみたいね。まだ、わからないの。これよ、これ」
ミサキはそう言いながら、指を三本立てると、優雅に上下に揺らした。
「姉さんを追い出すような真似するから、とっちめてやったのよ」
「とっちめるって。最初からはめるつもりだったのか」めまいがしてきた。
「そんなことしなくていいって言ったけど、ミサキが聞かなくて。散財させたわね」
「でも、高校生にもわかる工夫ってやりがいあったでしょ」と、ミサキ。
「じゃあ、源氏を教えてと、言ったのも、魂胆があってのこと?」
「誰に向かって書いているのか、わからない注釈なんて意味がないって、アドバイスする人がいたのよ」と、ミサキ。
ヒロがクスクス笑っている。ぼくはうなるしかなかった。
「でも、どうしてヒロとかタカオって偽名にしたの」
「いたずらよ。別に理由はないわ。でも、名前って不思議ね。名前と実態と、別なのかくっついているのか。まあでも、面白かったでしょ」
どう答えてよいのか戸惑っていると、玄関に音がした。
「時間通りだわ」と、ミサキが時計を確認する。十二時十五分。
「スペシャルゲストよ」と、ヒロ。
塾長が来てくれたのかと想像したが、入ってきたのはG書店のNだった。
「みんなからの礼だ」と、差し出したのは、発売されたばかりの『若紫』、定家自筆本の複製だった。
「塾もがんばってくれたし。もう源氏も解禁でいいわ」と、ヒロ。
「仕掛け人のご登場よ」と、ミサキ。
「そうか、おまえが仕組んだのか」
「まあ怒るな。それはそうと、講義を終えた今の感想は?」
「やり切った感と、やり残した気持ちと両方だな。中略で済ませてしまった所は是非読みたかったな」
「じゃあ、相手になろうか」と、N。
「今日はもう十分」と、三人が口を揃えた。
「ぼくも、もう疲れた。機会があったらまた」
ぼくは息苦しくなって窓を開けた。ニコライ堂の鐘が鳴っていた。
「護月」と題する小説を書き上げた時だった。突風で窓が開いたかと思うと、桜吹雪が舞い込み、原稿を巻き上げた。原稿用紙を拾い集め、窓を閉めようと窓辺に近づくと、復活祭を祝う準備だろう、普段聞こえることのないニコライ堂の鐘が、風にのって聞こえてきた。早く感染が終息し、世界中が〈復活〉を喜べる日が来ることを、願わずにはおれなかった。